全日本きもの研究会 続きもの春秋
7. 曲尺と鯨尺
呉服業界に入った人が誰でも困惑してしまう物に曲(かね)尺と鯨(くじら)尺がある。どちらも長さを計る単位で裁衣には欠かせないものである。日本の度量衡制度は1959年(昭和34年)にメートル法に統一され、現在では取引、証明上に尺貫法やその他の単位は使えないことになっている。しかし、呉服の仕立には尺、寸は今でも欠かせない。長年使ってきた裁衣の単位を法律で定めたからと言ってすぐに変えられないのは道理である。尺、寸の物差しをただちにメートルに改めよ、というのは為政者の横暴と言われてもしかたがない。
しかしながら、同じ尺に曲と鯨の二つあるというのも奇妙である。加えてメートルも含めれば三つの単位が呉服業界をまかり通っているのである。曲を「かね」と読ませる事とあいまって業界の新人が困惑しても無理からぬところである。
次のような笑い話がある。
呉服屋の番頭が新入りの丁稚に言った。
「そこの曲(カネ)尺とってくれ。」
「えっ、どれですか。カネ尺ですか?」
「それだよ、それ。そこに物差しがあるだろう。」
「これですか。これは金(カネ)じゃなくて竹の物差しですよ。」
私が初めに呉服業界に足を踏み入れたのは京都である。関西では鯨尺が多く用いられる。しかし、東北では曲尺が多い。鯨尺に慣れた私は今でも曲尺で言われるとぴんとこない。

尺の起源は中国にある。元々は、『手を布(し)きて尺を知る』と言う孔子の言葉通り、手を広げて物にあてた長さだったけれども、長い間に長さの基準が変化してきたという。(孔子は身長が180センチもあったと言うので、孔子の掌は広げれば30センチも有ったのかも知れない。)
曲尺は土木建築用に用いられた物で、周代に発生して今日まで変わっていないという。曲(かね)という字は文字通り「まがり」を意味し、中国で使われたのは日本の大工道具の差し金を意味していた。現在の曲尺は明治政府によって33分の10メートルと規定されている。
一方、鯨尺は裁衣用に後で作られた単位である。室町時代には曲1尺2寸をもって呉服尺としたものを江戸時代に入ってからさらに5分延ばし、曲1尺2寸5分を鯨1尺としたものである。鯨尺の名称はクジラのヒゲで物差しが作られたことに由来する。
江戸時代には呉服尺、鯨尺ともに使われていたが、1875年(明治8年)明治政府は呉服尺を廃して鯨尺を残した。それでも曲尺と鯨尺という二つの単位、それも同じ尺という単位が使われてきたのだから、度量衡の統一という流れに逆らっていたことには間違いない。
日本の尺貫法で1尺は10寸である。これは曲も鯨もかわらない。そして、10尺が1丈である。十進法はここまでで、丈の他に「間」という単位がある。6尺が1間である。そして60間が1町、すなわち360尺。そして、1里が36町、すなわち2160間、12,960尺である。十進法できちんと定められたメートル法では考えられない面倒な単位である。
呉服で使う長さの単位には他に「反」「疋」がある。一疋は二反である。
一反は着物一枚を仕立てるのに必要な長さで、現在呉服業界では一反のことを三丈物(鯨尺で三丈)と呼んでいる。裾回し(八掛け)を共布で作るときや振袖用はもう一丈必要とするので四丈物と呼んでいる。従って疋物は六丈である。江戸時代には一疋は曲尺で八丈と定められていたため、疋物を八丈物と呼び、黄八丈もその呼び名の名残りである。
さて、それでは店に並んでいる反物は鯨尺で三丈の長さなのかといえば必ずしもそうではない。反物に添付した長さの表示を見ると、12.2m、12.4m、11.8mと、様々である。一反は何尺というはっきりとしたきまりはないのである。さらに次のような会話を聞くことがある。
「これは綿反ですから12mはありません。」
反物には縮緬等の絹物や綿麻の反物がある。絹物の反物は長く、綿反は短いという訳である。呉服の用語辞典で「反物」を引けば、
『仕立てるものが具合よく一着分とれる幅と丈をもつもので、この寸法を備えたものを一反と数える。木綿反は鯨尺で2丈6尺(9.85m)~2丈8尺(10.61m)。絹物は3丈3尺(12.51m)』
と、あった。
反というのはあくまでも度量衡に定められた長さの単位ではなく、きものを仕立てるのに要する生地の長さを表わすのである。では何故綿反は短く絹物は長いのか、出入りの綿反屋さんに聞いてみた。 「そりゃあ綿反は絹物と違って・・・。」
以下、その綿反屋さんが語った理由である。
絹布はそれ自体高価だけれども、商品になる時にはそれ以上の付加価値がついている。友禅染や草木染、また刺繍や金彩を施して生地の数倍、数十倍の付加価値を付けて市場に出る。それ故一寸二寸の長さをけちる必要はない。そして、もしも染め上がってから用尺が足りなければ、その損害は莫大なものとなってしまう。
そんな訳で絹布は一着の着物を仕立てるのに十分な(最大の)長さをもって一反としている。しかし、綿布の場合、絹布のように高い付加価値を付けることは少ない。半纏や真祝など筒染で染められる芸術的な商品も有るけれども、ほとんどは白生地で売買される。また、利鞘も絹布ほど大きくないので綿反屋にしてみれば一寸の長さの違いは利益に大きく影響するのだという。晒を一反あたり一尺長く作ることは採算の面で大きな問題である。
したがって綿反屋は許される範囲内で一寸でも短く一反を設定したがるのである。絹布の一反は長く、綿布の一反は短いのはそんな理由だろうと言うのである。
綿反を商う現場の声としてはうなづける話である。綿反が短い理由はそればかりではないかも知れないが、そんな理由も間違いなくあるのだろう。
はっきりとした長さを決めずに、反、疋という単位を定めた日本の文化は西洋では考えられないものかもしれない。しかし、日本では、そのような単位の決め方は他にもある。
時刻を表わす九ツ、八ツ、七ツという単位がある。「時そば」という落語で御存じの方も多いと思うけれども、どういう単位なのかを知っている人は以外と少ない。
真夜中零時を九つとして、日の出を明け六つ、日の入りを暮れ六つとしたものである。午前零時は九つ、午前二時が八つ、午前四時が七つ、午前六時が六つ、午前八時が五つ、午前十時が四つ、そして正午が九つである。それぞれ二時間毎の表示なので間をとって半をつける。すなわち六つ半は七時である。
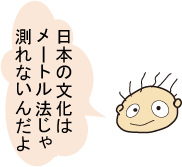
しかし、これらは現代の時刻の規準に合わせたおおよその時刻である。九つは午前零時と正午には間違いないけれども、日の出は午前六時、日の入りは午後六時とは限らない。夏の日の出は早く、冬は遅い。夏は昼間の一つは長く夜は短い。冬はその逆になる。季節により一つの時間の長さが異なるのである。
日本のエジソンと言われる久留米の田中儀衛門が日の出、日の入りに打つ寺の鐘を自動的に鳴らす装置を作ったと言う。しかし、時刻を計測した季節と、完成した季節が違っていた為に、まだ暗いうちに明け六つの鐘が鳴ってしまったという話があった。日本の時刻の不合理さを表わす逸話である。
しかし、日の出から日の入りまでの時間を等分して時刻とする、というのは見方を変えれば合理的でもある。自然に身をまかせずに時計に振り回されている現代人の方がよほど不合理かもしれない。
反や疋という単位もきものを仕立てるのに必要にして十分な長さを表わしただけなのである。
曲尺と鯨尺、反物疋物、そして明け六つ、暮れ六つ、いずれをとってみても日本の文化は曖昧な中に合理性を含んでいるのである。西洋の考え方に慣らされた現代人には理解しにくいかも知れないが、その辺りを理解しなければ、きものは不合理で扱いにくいものとしか映らないのではないだろうか。

