全日本きもの研究会 きもの春秋
17. 悉皆(しっかい)について
きものの関連業種に悉皆屋というのがある。悉皆とは反物の染色、染め直し、洗い張り、染み抜きなど、きものに関する一切合財のメンテナンスを言う。
私は修業の為に京都の呉服問屋に入社した。二年で家に戻らなくてはならない事情があり、短期間に呉服の事を覚えなければならなかった。短期間できものの事を覚えるならば悉皆の仕事をするのが一番という会社の配慮があり、入社して三カ月間悉皆担当の仕事、つまり悉皆屋まわりをさせられた。
今にして思えばなるほどその三カ月間はきものについてのあらゆる知識を吸収する良い期間だったと思う。仕事の内容は、店の商品や取引先から送られてくる商品を悉皆屋にまわして加工するものだった。
当時まわった悉皆屋は、染み抜き、焼け直し、洗い張り、湯のし、紋入れ、仕立て、染色、掛け接ぎ等、ありとあらゆるきもののメンテナンスだった。
京都の町は烏丸通りや五条通り、四条通り、御池通りなどの広い通りを除けば昔ながらの軒先が触れ合うような細道がほとんどである。自転車や軽自動車に乗って京都の町を走り回り、加工する商品を運び、そして回収するのが私の仕事だった。
悉皆の仕事をすれば、京都の町が呉服の町であることが良く分かる。西陣に行けば機屋が軒を連ね、室町には数え切れないほどの問屋が並んでいる。西陣や室町は誰の目にも呉服の町に映るけれども、西陣や室町を離れた一見町屋のような所にも、呉服を支える悉皆屋さんが沢山あった。
湯のし屋さんは、長屋のような京都の家の玄関を入ると、台所のような板の間で湯気が吹き上がる煙突の上に反物を張って、湯のしをしていた。縫い紋を頼みに住所をたよりにたずねたら、家庭の主婦(縫い紋の熟練者であろうが)が内職に縫い紋をしていた。染み抜き屋、かけつぎ屋等いずれも普通の町屋だった。悉皆という仕事を通して、京都の町が呉服を支えている事が良く分かった。
悉皆の仕事をする上で、最も気を使うのは、染み抜き、焼け直し、掛け接ぎ等の直しと呼ばれる仕事である
しみぬき
絹の生地はしみになり易く、又きものの性格上しみが付くことを極端に嫌っている。縮緬や羽二重に水が付くとたちまちしみが出来てしまう。私は小さい時から店の品物に水を付けないように注意されてきた。お店で水を飲もうとすると、品物に水が弾けるから店では水を飲まないように、濡れた手で店に出れば手を拭くようにと口を酸っぱくして言われたものだった。水はしみを作るものと知らず知らず頭にこびりついていた。
小学校に入り家庭科の授業で先生に、
「衣服にしみを作る原因になるものには何があるでしょう。」
と質問された。その家庭科の先生は、泥とか果汁、油等の解答を求めたのだろう。私は真っ先に手を挙げ自信を持って
「水。」
と答えた。先生に
「えっ水ですか。水ではしみにはなりませんね。」
と言われ、友人達にも笑われてしまった。その頃の私はひねくれていたのか、反論することもなく、
「家庭科の先生って割りと物を知らないんだなぁ。」
と独言のように頭の中でつぶやいたことをはっきりと覚えている。
家庭科の先生の言葉を借りるわけではないが、しみを作る原因には何があるだろう。お客様より持ち込まれるしみぬきの原因の主なものとしては「泥はね」「ファンデーション」「汗」「お酒」「ジュース」「血液」「ドレッシング」「口紅」「子供のよだれ」「子供の手垢」等である。おもしろいものでは「子供の小便」というものもあった。
大切なきものに、しみが付いてしまうと大抵の人は驚いて焦ってしまう。それが弾けたドレッシングであろうと、こぼしたお酒であろうと。ましてソフトクリームをべったりと付けようものなら気が動転してしまう。すぐに拭き取ろうとするのは人情である。大抵の場合はハンカチやナフキンで拭き取ったり、水に付けて擦ってしまう。
和服のしみぬきの技術はたいしたものである。普通の人が染み抜きに対して思っているものの数倍の技術があると思って差し支えない。言わば、どんなしみでも元通りにきれいに抜いてくれる。花粉や墨汁など非常に取れにくいものもあるけれども、特殊なものを除いて九割りは直してくれる。ただし、これには条件がある。京都でしみぬき屋を回っていたときも今もしみぬき屋さんに言われることである。
1、絶対にあわててしみの付いたところを擦らないこと。
2、できるだけ早くしみぬきに出すこと。
3、何でできた染みなのかを明確にすること。
これらの条件さえ満たされれば、しみぬき屋さんはあたかも魔術師のようにしみを抜いてくれる。
しみがついて、あわてて生地をこすってしまえば、繊維の組織を壊すだけではなく、しみが繊維の奥へ奥へと入ってしまう。仮に、しみをうまく取ったとしても擦った後が残ってしまう。しみを擦ればいくらかでもしみが取れたように思えるけれども、しみぬき屋さんにしてみれば、しみが多かろうと少なかろうと大した問題ではない。しみが取れ易い状態で持ち込まれたか否かが問題なのである。

ソフトクリームのように、べったりと付いてしまった時には、そのままでと言うわけにはいかない。その時には、生地を痛めないように軽く拭き取り、水を掛けて両側からハンカチを充てて軽く叩くようにすれば良い。乾いた布でしみの部分を挟み、しみが他にうつらないようにしてしみぬき屋に持ち込めば、しみを完全に抜いてくれる。
大切なきものに、しみが付いても冷静に対処するのは余程難しいらしい。私の店の仕立て屋さんにも誤ってしみを付けた時には、そのまま持ってくるように言っているのだが、つい擦りたくなるらしい。しみが付いても冷静に対処することがしみぬきの極意である。
ほとんどのしみは抜けます、とは言うものの、古くなったしみはその保障の限りではない。時々古くなったしみを持ち込まれることがある。
一目で古いしみと分かるので、いつごろのものかと尋ねると、五年から十年前のしみだと言う。五年十年経ったしみは取れないと思った方が良い。本人は十年も放っておいたつもりは無いのだろうが、タンスから出してみたら、しみが付いていたと言うことらしい。
しみが付いていたのを見落として、という場合もあるけれども、汗が付いていたのを知らずにタンスに仕舞い込み、十年経って汗の付いたところが黄色くなっていたというケースが多い。長年タンスに仕舞い込むようなきものは要注意である。
きものを着た後は衣紋掛けにきものを掛けて陰干しして、しみが付いていないかをチェックする事が大切である。しみや汚れがあれば、それが何のしみかが分かればしみ抜きがしやすくなる。病気の原因が分かれば対処療法もたて易いというところである。
最近のホテルでのパーティーでは、お酒やドレッシングによるしみが多い。サラダのドレッシングが野菜ではねて胸元にしみをつけてしまうケースを良く見掛ける。きものを着慣れているお客様が頻繁にお酒のしみを持ち込むようになった。
「奥様のように着慣れてらっしゃる方がなぜ・・・。」
と聞くと、きものの環境についての問題が浮かび上がってきた。
きものは決して汚してはならないもの、大切に扱うべきものという原則は、きものを良く着る人には当然のことだけれども、きものを着たことの無い人にとっては、きものも洋服も同じ感覚であるらしい。
お酒を注ぐのも無頓着でお酒をこぼしてしまったり。お酒のついた手で、
「やあ、奥さんしばらく。」
と肩に触れてくる殿方が後を絶たないという。
最近、ホテルのボーイさんのお酒を運ぶ盆が、きものを着ている人の肩をかすめていくのを良く見掛ける。はらはらして見ているけれども、これもきものが日本人に縁遠くなった証左なのかと思ってしまう。
しみぬきに関しては、しみを作らない様にするのが一番良い方法であることは言うまでもないことである。
やけ直し
色の付いたものは布であれ紙であれ、光が当たれば多少なりとも色やけしてしまう。染料の種類や染め方でもその堅牢度は異なるが、一般的には織物(先染)よりも染物(後染)の方が色が飛びやすい。色の中では藤色系統が良く色やけする。
きものをたたんでおくと、その折り目の部分が光(必ずしも強い光ではない)にさらされ、線状に色やけしてしまう。又、仕立て上がったきものを洗い張りしようと解くと、縫目に沿って縫い込まれていた部分と外に出ていた部分が焼けて、はっきりと分かってしまう事が有る。
色が焼けるのは必ずしも強い光に当たったときばかりではない。室内の弱い光でも長い間あたっていると、色やけをおこすのである。
私の店で新装後一年程して空調設備の修理の為に天井の壁紙を一部張り替えた事があったけれども、張り替えた後がはっきりと残ってしまった。きものに限らず色のついているものはすべて時間とともに色が変ると思ったほうが良いらしい。
きものの場合、色やけが生じたら、 「しょうがありません。」 で済むことではない。特に高価な友禅などは色やけが生じた場合、直せるか否かは深刻な問題である。
高価な加賀友禅がやけてしまったと持ち込まれた事があった。そのお客様がたいそう気に入っていた品物なので娘に譲ろうと洗い張りをして仕立て直したところ、娘さんの寸法が大きかったため、袖付けや身頃にやけ跡の筋が入ってしまった。仕立てる時に気がつきそうなものだが、やけ跡を気にせずに仕立ててしまったらしい。
地色が青で、青の濃い部分と色やけした薄い部分の境目に線が入り、一見して色やけと分かってしまう。御客様の思い入れのあるきものなので、何とか直してほしいと言う。
早速、直し屋に持ち込んだ。直し屋さんは六畳間位の小さな部屋で四~五人が仕事をしていた。職人さん達は皆正座をして仕事をしている。仕事をするときには正座をするように、とはその直し屋の主人の言だった。
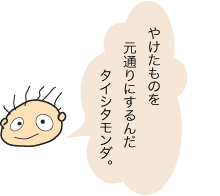
青色の染料を薄く溶かして、焼けた部分に刷毛で染料を刷り込んでいく。染料がとても薄いので、何度染料を刷り込んでも私の目には全く色が変わらないように見える。それでも、じっと焼けた跡を見つめて、
「はい、それでは○○日までに直しておきます。」
と言ってくれた。私は本当に直るのかどうか心配だった。
数日後、直しの終わった品物は、直し屋に持ち込んだ品物とは全く別もののようだった。筋の入っていた焼け跡は見られない。鵜の目鷹の目で見れば、ここが焼けの跡だろうと予測がつくけれども、何も知らない人に見せれば焼けた品物とは思いもよらないだろう。
染物のきものは、格別強い光にあてなくとも、長い年月の間には、色やけすることを覚悟しなければならない。きものの運命と云ってしまえばそれまでだけれども、それをフォローする直し屋さんがいてくれるのである。
掛け接ぎ
「掛け接ぎ」という言葉を知ったのは、京都で悉皆の仕事をしてからだった。本当は小学校の家庭科あたりで、あるいは聞いているのかもしれないが、私は家庭科の授業は調理実習以外に興味はなかった。
先輩の社員に、
「今日はおもしろい所にいくから一緒についてこい。」
と言われ、掛け接ぎ屋についていった。途中、車の中で、
「おもしろいオヤジさんだから笑うなよ。」
とも言われた。
そのかけつぎ屋は、御池通りに面した(と思う。記憶が定かでない。)古い京都の町屋だった。玄関を入り、
「まいど、おおきに。」
と声を掛けると、主人が出てきた。年の頃は六十代後半、六月ともなれば京都はむし暑い日があり、白絣に兵児帯という姿だった。薄くなった頭髪を真中から分け、それを隠すために頭皮に墨を塗っている。丸い眼鏡を掛け、チョビひげをはやしている。
成程、初対面の人は笑ってしまうかも知れない。例えてみれば、明治時代の町医者といった風情である。本人も自覚しているのだろう。玄関には「○×絹医堂」という古い看板が掛けてあった。
絹医堂、すなわち絹のお医者さんである。その立派な看板と、主人の(以後、先生)滑稽ながら威風堂々たる態度に「絹医堂」とは只の洒落ではない様に感じられた。布が破れることにはそれまで何の感慨もなかったけれども、この時、絹に対する日本人の伝統的な一面を見たように思った。
狭くて急な階段を上がり二階の四畳半の仕事場に入った。古い造りの格子の窓から御池通りの木々が見える。仕事場はお茶室のように、喧噪な京都の街の中の静寂な空間だった。
持ってきた品物を見せ、破れた所を直してくれるように頼んだ。値段の交渉である。はっきりとした価格表があるわけではない。生地の破れ具合、生地の種類、またその商品の価値などを総合的に判断するらしい。
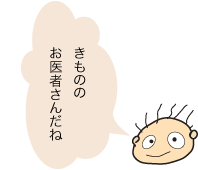
その時持ち込んだ品物が何であったか、そしていくらで直してもらったのか覚えていないが、1センチあたり一万円位の相場だったと思う。ちょっと引っかけた破れを直すのに一万円である。ずいぶん高いようにも思えるけれども、数百万円もする加賀友禅や何らかの思い入れの有るきものが元通りになるとすれば安いものかも知れない。それにしても、破れたものが本当に元通りに成るのだろうかという思いは拭い去れなかった。
私が初めてうかがったので、先生はいろいろな話をしてくれた。
「これは俺が直したんだ。どこを直したのか分かるか。」
と見せてくれたのは疋田絞りの生地だった。なるほど、見てもどこを掛け接ぎしたのかが分からないほど良くできている。
「どうじゃ、分からかんじゃろう。触れば分かるけどな。」
と言って裏返しにして見せてくれた。
掛け接ぎは布の端を突き合わせて接ぎ目が表にひびかないように縫い合わせている。触ったり、裏から見れば掛け接ぎの跡ははっきりと分かるが、その先生の直したものは表からは全く分からない。先生は時計屋が使うルーペを使って糸を一本一本入れていくんだと言っていたが仕事をする所は誰にも見せなかった。
その後も幾度か掛け接ぎを頼みに先生をうかがったが、できばえは只々感心するばかりだった。紬のように目の粗い物は、なんとか接ぎ跡をごまかせるような気がするが、縮緬や綸子の様な目の細い生地も全くと言って良いほど接ぎ跡が分からなくなってしまう。
私がその先生の所に出入りしていたのは、もう十年以上も前の事であるが、あの先生は今も仕事を続けているのだろうか。目を酷使する仕事なので視力が衰え、嘘か誠か知らないが、
「片目を摘出するんだ。」
とも言っていた。あのようなすばらしい技術が受け継がれれば良いが、もし技術を受け継ぐ者もなく損なわれていくのであれば、何とももったいないような気がする。
最近、母が父のスーツをクリーニング屋に掛け接ぎに出していた。何を引っかけたのか衿の所が数センチ破れていた。掛け接ぎと聞いて、私は京都の掛け接ぎ屋を思い浮かべていた。掛け接ぎは高い物と思うと同時に、目の粗いウールの生地など跡が全く分からなくなるだろうと思っていた。しかし、仕上がったスーツを見て私は驚いてしまった。破れた跡は分からなくなるどころか前よりも破れが目立っている。これでは掛け接ぎではなく、接ぎ当てである。とてもスーツとして人前で着られた物ではない。
同じ掛け接ぎでも何故このように違うのだろうか。値段が高いから、安いからの問題ではない。やはり洋服ときものの認識の違いではないだろうか。きものは大切に扱うべきもの、良い物は子や孫に伝えるものという認識が、あのような高度の掛け接ぎ技術を生んだのだろう。衣服は消耗品という洋服の感覚はきものには無いのである。
「しみぬき」「やけ直し」「掛け接ぎ」という、きものの悉皆の仕事について触れてきたけれども、それぞれが長い伝統に支えられた高度な職人の技術である。
京都で悉皆の仕事を見てきた私は、きものには魔術師がついている、という感じさえ抱いた。汚そうが、やけようが、破れようが、いくらかかるかは別として、ちゃんと元通りに直してくれる。
山形に戻り、汚れややけの品物に直面した事もあったが、その度に魔術師達に助けられたのは言うまでもない。
悉皆にはまだまだいろいろな技術があるが、どれを取ってみても、きものを大切に扱い、長く着る為のメンテナンスである。
このような高度な技術は、世界に誇れるものと思う。しかし、一方できものの需要の減少でこういった技術が失われ、きものは高くて扱いにくい物といった不評ばかりが独り歩きすることを私は恐れている。

