全日本きもの研究会 きもの講座
3. 夏のきものとゆかた
夏のきものの話をします。もう夏も終わろうとしていますので、本当は夏のきものの話はもっと前に、七月頃にした方が良かったかもしれません。実は七月といえば土用、土用と言えば鰻です。この会場の揚妻さんは鰻の老舗。七月はとても忙しく今月となった次第です。
きものは年に三回衣替えすることは御存知でしょう。袷、単衣、薄物の三つです。京都の舞子さんは年に四回衣替えするのですが、普通の人は三回です。この中で夏のきものと言われるのは「うすもの」です。
薄物というのは文字通り薄くてほとんどが透ける素材でできています。 「うすもの」と言うのに「薄物」という字を充てましたが、きものの用語辞典などで調べますと、「うすもの」は「羅」と書いてあるものがあります。語源を調べますと、「うすもの」は「羅」の事で、必ずしも夏物を表す言葉ではなかったように思えます。しかし、一般には夏物を「うすもの」と称しています。誤解を免れようとするならば、夏物は「うすもの」とは言わずに「夏物」と言った方が良いかも知れませんが、ここでは袷、単衣、に対してやはり「うすもの」と呼ぶことにします。
袷と単衣の違いは裏が付いているか否か、という事であります。単衣用の生地もありますが、基本的には袷と単衣の生地は同じです。
刺繍したものですと裏が擦れるので単衣には適さないとか、絞りは膝や肘の当るところが伸びてしまいますので裏打ちしなければならず袷に仕立てるということはありますが、生地そのものは袷も単衣も同じ物です。
夏物はと言いますと、裏が付いていないのはもちろんの事、生地そのものが袷や単衣とは異なります。初めに申し上げましたように、夏物は透ける生地を使います。
主な薄物の生地としては「絽」「紗」「羅」があります。
透ける生地を織るには、経糸または緯糸の間に隙間を造らなくてはなりません。糸の間隔を開けて織っただけでは糸が寄ってしまい、生地になりませんので、隙間を造りながら経糸と緯糸を固定する必要があります。その為に捩り織という技法が用いられます。
絽は間隔を置いてスリット状に隙間を開けたもので、隙間と隙間の間の緯糸の数で三本絽、五本絽があります。また、経にスリットを配した経絽もあります。
紗は経糸緯糸を一本ずつ等間隔に隙間を造った生地です。
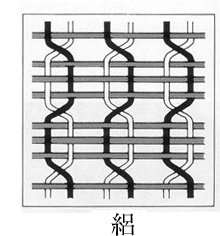
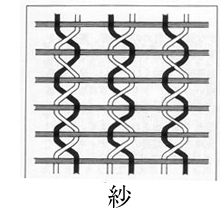
羅は図のように、経糸が左右の糸に複雑に絡み合いながら織られるものです。中国では漢の時代から織られ、日本では奈良時代に伝わり正倉院の御物にも納められています。しかし、織り方が複雑で難しいために、その技法は途絶えましたが、大正時代に入って西陣で再び織られるうになりました。羅は紗に比べて目が粗く、きものには適しませんので主に帯として織られています。
羅というのは中国語では鳥を捕える為の網や篩という意味があります。大体のイメージは分かると思います。
商品としての羅は帯地やコート地として売られていますが、実はその内の多くは正確に言えば粗紗と呼ばれる織物です。粗紗というのは文字通り粗く織った紗という意味です。組織は紗の組織なのですが、非常に目が粗く、一見羅のように見えるからです。
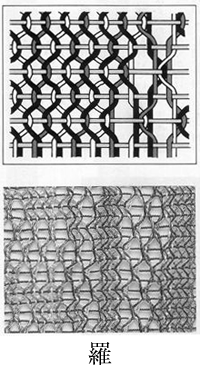
うすものにも袷と同じように訪問着や付下げ、小紋、色無地などのアイテムがあります。
留袖や振袖にもうすものはあるのですが、最近はお目にかかりません。私は絽の留袖を二枚だけ売った事があります。夏の留袖と言うと、余り用途がないように思えますが、一つは謡曲をなさる方がお召になります。夏でも舞台では黒留袖が必要なのでしょう。また、夏の結婚式といえば余りなさそうですが、最近は色々な理由で夏も結婚式があるようです。しかし、絽の留袖まで吟味される方は少ないようです。
振袖はまだ売ったことは無いのですが、京都にいた時に一度だけ絽の振袖を見た事があります。染屋さんも今はほとんど染めていないようです。しかし、昭和初期頃のきものをお客様から見せていただく事があるのですが、絽の振袖は良く見られます。絽だけでなく、綿入れの振袖もありまして、昔は振袖であれ留袖であれ四季を通じで着ていたようです。
訪問着や付下げ、小紋、色無地などには絽が多く使われています。紗は盛夏用と言われていますし、友禅を施すには絽の方が適しているからでしょう。
絽の中には、絽縮緬と呼ばれるシボの高い絽もあります。絽縮緬は六月半ばの単衣の頃から九月中旬まで着る事が出来ます。色無地の一つ紋付や暈しの無地などは着る機会が多く一枚有れば重宝するようです。
夏のきものに浴衣は欠かせません。最近は若い人の間に浴衣に対する関心が高まっているようです。私の店の前を通る女子高生が、飾ってある浴衣を見て、
「あっ、浴衣だ。欲しいなぁー。」
と話す姿がよく見受けられます。
浴衣の語源は湯帷子(ゆかたびら)であることは御存知でしょう。湯帷子というのは、昔入浴の時に用いた衣で、風呂には裸では入らずに湯帷子を着たまま湯に浸かっていました。素材は水に強く、水切れの良い麻が使われていました。
では、この帷子(かたびら)というのは何かと申しますと、「帷子」の語源は「片枚」でして一枚物すなわち単衣を指して言っていました。つまり、湯帷子というのは湯に浸かる為の単衣の衣という意味です。
帷子という言葉は昔は単仕立のきもの全てを指して言っていたのですが、江戸時代には絹物を単衣、麻素材の物を帷子と区別していたようです。
湯帷子は湯に浸かる為の衣でしたので、もちろん対丈ですし、柄など無い麻の白生地で作られていました。しかし、湯帷子を着れるのは上流階級に限られ、庶民はとても着れるものではなかったでしょう。
近世に入ると庶民も豊かになります。いつからそうなったのかは分かりませんが、湯帷子は湯上がりのくつろぎ着として庶民に普及しました。初めはくつろぎ着ではなく、入浴後の汗取り、水切りに使われたとも聞きます。ちょうどバスローブのような使い方だったのでしょう。
湯帷子が浴衣となって庶民のくつろぎ着となり、盆踊りの時に着たり(踊り浴衣、または盆帷子)、役者が楽屋で用いたり(楽屋浴衣)するようになりました。そうなりますと浴衣にもファッション性が出てきまして様々な染が施されるようになります。それは現在の浴衣の原型と言えるものです。
浴衣の染につきましては後にお話しますが、浴衣が湯帷子から発生したという事を覚えていてください。浴衣を理解するキーワードになりますので。
さて、浴衣は数あるきものの中の一つと思われています。確かにその通りなのですが、きものと浴衣の間には一線を引かなくてはなりません。
江戸時代以降、普段着であれ晴着であれ、一枚で着るということはありませんでした。きものを着る時には襦袢を着て襟を出します。夏でも素足ということはなく、足袋を履いて帯を締めます。帯は略式に半幅帯を締めることはありますが、通常太鼓に締めます。
しかし、ゆかたを着る場合、下着は着ますが襦袢は着ません。足袋も履きません。帯は半幅帯か兵児帯を締めて太鼓は造りません。
ただし、特殊な場合、例えば踊りの時や芸者さんなどが浴衣に太鼓帯で足袋を履くということはありますが、通常は上記の通りです。
浴衣は湯帷子から起こった物と解せばこの事は理解できると思います。
一般に浴衣の素材に使われているのは木綿です。いわゆる通常の浴衣に使われている木綿も見た目は余り変らないかも知れませんが品質によって種類があります。コーマという生地が最高です。コーマというのは木綿の短い繊維を取り除き、長い繊維だけを残したものですので毛羽立たず柔らかいものです。他に徳岡、天竺などがありますが、それぞれに品質の差が価格に響いています。
コーマや徳岡の浴衣は襦袢を着ずに浴衣として着られます。これに対して高級浴衣と称される綿縮や麻(小千谷)、綿紅梅、絹紅梅、しじら、などは浴衣としても着られますが、襦袢を着て足袋を履き、太鼓帯を締めれば十分に街着として着られます。これらは浴衣ときものの接点にあると言えます。
浴衣の染色法も様々です。
その一つに長板中形という染があります。江戸時代から明治にかけては浴衣の主流となったもので、いわば浴衣の染の源流と言えるものです。約六メートルの板(長板)に反物を貼り付けて型を置いて糊を摺り込んで行きます。表に全て型を入れると、今度は裏返しにして裏側にも表と重なるように型で糊を入れて行きます。表だけに糊を入れても裏側から染料がしみ込みますので裏側にも糊を入れて染料の侵入を防ぐわけです。口で言うのは簡単なのですが、非常に精緻な型ですので、裏表にずらさずに糊を入れるのは至難の技で熟練の職人仕事です。昔はこのように浴衣は手間ひま掛けて一枚一枚手で染められました。
「かたづき」という言葉を聞いた事があるでしょうか。御年配の方が良く口にされるのですが、「かたづき」なのか「かだづぎ」なのか良く分かりません。山形弁なので濁音が入っているので本当は「かたつき」なのだろうと思いますが、きものの本や用語辞典には出てきません。山形地方だけで使われる言葉かもしれません。
この「かたづき」の意味するところは浴衣です。話す人によってはもう少し高級なきものを指しているようにも思えるのですが、とりあえず「かたづき」イコール「浴衣」と解して良いようです。
関連記事
「きもの春秋 6. ゆかたの比翼」
「きもの春秋 11. 浴衣(ゆかた)」
「きもの博物館 9. 絞りのゆかた」
「きもの博物館 23. 紗…日本の情緒」
「きもの博物館 41. 紗合せ」
「きもの博物館 50. 上布」
「きもの博物館 51. 芭蕉布」
「きもの博物館 61.平織麻襦袢(ひらおりあさじゅばん)」
「きものフォトトピックス 3. 昭和41年の夏大島」

