全日本きもの研究会 きもの春秋
15. 手造りと難物の境
15. 手造りと難物の境
きものの織や染は昔から手造りで創られてきた。「手造り」という言葉ははっきりとした範疇が有る言葉ではなく、今ではわりと曖昧に使われることが多い。
「自然食品」という言葉が問題となり新聞に取り上げられたことが有った。「自然食品」とは何か、という事になると、余りはっきりとした定義はない。事は人間の口に入る物の事などで、放っては置けないと、厚生省や公正取引委員会がのりだし、まがりなりにも「自然食品」の定義に線引きをしたという記事が載っていた。
「手造り」「自然食品」、どちらを取ってみても現代人には響きの良い言葉である。しかし、考えてみればおかしな話である。きものに限らず生活用品は昔から手造りであるし、食品は自然の恵みとして人類は太古の昔より享受してきたはずである。
現代、「手造り」「自然食品」の言葉がもてはやされるのは、対極にオートメーション、機械化、大量生産という産業革命以来の物造りの常識変化があるのだろう。

きものの世界でも
「これは手描きですか」
「これは手機(てばた)ですか」
という言葉を良く耳にする。ここでも職人の手によるきものや帯が珍重され、ありがたがられている。しかし、その現象の裏にはちょっと困った問題も起きている。
手描きの友禅や手織りの帯には、プリント物や機械織りの物には無い深い味わいが有る。
染め物に関して言えば、染めの種類によって「手描き友禅」「型染め」「プリント」等がある。「型染め」も「本型染め」と言われるものは職人の手に掛かる手造りである。プリントの染め物に比べて手描きの友禅ははるかに手間が掛かる。
下描きから、糊で糸目を引き、色を注す等沢山の工程を経て染め上げられる。その手間を考えれば高価な事もうなずける。手間をかけたから、高価だからといって必ずしも良い作品だとは限らないけれども、手描きの染物にはプリントでは絶対にまねのできない味がある。それでは、手描き(手造り)の良さとは何処に有るのだろう。

江戸小紋という染物がある。江戸小紋は昔、大名達が裃(かみしも)に使った柄で、非常に細い型染めである。その柄は藩の「定め紋」「御留柄」として他藩では使用できない事になっていた。ちなみに「鮫小紋」は紀州家、「菊菱」は前田家、「胡麻柄」は鍋島家というように。
江戸小紋には鮫小紋を始めとして、角通し、万筋など沢山の柄が有る。特に鮫小紋が有名だけれども、鮫小紋は細い点を鱗状に配した模様の小紋である。
江戸小紋の製作は型紙を作ることから始まる。伊勢型紙と呼ばれる柿渋を塗った紙に柄を彫っていく。鮫小紋や角通しでは彫る穴が細いほど良い。細いだけではなく、穴の大きさが一様で間隔も一定でなければならない。
万筋は細い線をできるだけ細く、太さが一様になるよう彫らなくてはならない。最も細い「毛万筋」と呼ばれる柄は1寸(約3センチ)の間に31本の線を彫っていく。線を引くだけならば、できそうな気もするけれども、最初と最後の線の間隔が一定でなければ繰り返し染めたときに、線は、ずれてしまう。単純な仕事のようだが、忍耐と神経を極限まで消耗する職人技である。
できた型紙で、今度は染め職人の手で生地に染料を刷り込んでいく。型の長さは3~4寸(約9~10センチ)、一反の反物(約12メートル)を染め上げるには、約百回型紙を移動しながら染めなくてはならない。下手な人が染めれば、型紙と型紙の間がずれて、横に線が入ってしまう。型紙がずれないように、色が一定になるよう染めるのは至難の技である。これも熟練の職人でなければできない仕事である。
いくら熟練の職人でも、型が全くずれるいように染めることはできない。一反を染める間には何ヶ所かは数分の一 、あるいは数十分の一の単位で型がずれる場合が有る。余りにそのずれがひどい場合には「おしゃか」となるけれども、許容範囲であれば、ずれを目立たなくする「地直し」という工程を経る。
この「地直し」というのも職人技である。焼け直しとは違い、細い柄のずれを目立たなくすると言うのだから、どのようにして直すのかは分からないが、地直し職人の手にかかれば、たちまち作品に命が吹き込まれてしまう。
型を彫る職人(彫師)、染め職人(染師)、地直し職人、いずれの仕事も熟練を要する職人技である。しかし、実は作品ができるまでには、型地紙を作る職人や縞柄を作るときに必ず必要な「糸入れ」等、目立たないが、まだ数多くの職人仕事を必要としている。
それらの手を経てできあがった作品は、すばらしいものである。鮫小紋や角通しであれば
「よくもまあ、こんなに細かく」
万筋であれば
「よくこんな細い線を」
と感心する細い柄が整然と、あたかもコンピューターが設計した半導体素子のように染められている。
コンピューターと言えば、伝統的な産業である呉服業界にも最新科学技術が取り入れられている。「きもの春秋8.西陣の帯」の中で触れたように、職人の手を介して手間ひまかけて作られた紋紙は、フロッピーデスクに取って変わっている。染物でもプリントの技術が発達して安価に染物が作られている。
江戸小紋は、出来るだけ細かく、整然と(乱れないように)染めるのが良い、と言ったけれども、最新のプリントの技術をもってすれば、手で作るより細く正確に染めることができる。手彫りの万筋柄では一寸幅に三十一本彫るのが限度だけれども、プリントでは一寸幅に三十六本の万筋柄が染められている。理論的には、まだまだ細い線を引くことが可能だという。人間の手では到底及ばない細く正確な万筋柄である。鮫小紋や他の江戸小紋もプリントで染められ、価格は手彫りの物の数分の一で売られている。
手彫りの江戸小紋よりも細く正確に彫られたプリント物のできばえは、と言うと比べてみれば一目瞭然である。どちらが良いかと言えば、百人中九十九人が手彫りの物を揚げる。たいしてきものに興味のない、目の無い人であっても結果は同じである。
細く正確に作り出すコンピューターの柄は、いわば手本である。その手本の柄に少しでも近づく様にと努力して作った江戸小紋が何故、正確無比な手本とも言えるプリント柄よりも良く見えるのだろう。
手造りの良さとはその辺にあると私は思っている。
二つの江戸小紋を比べてみよう。プリントで染められた柄は確かに柄は驚くほど細く整然としている。しかし、少し離れて見ると、余りに整然と細い柄が並んでいるので、無地にしか見えない。印刷の「網かけ」と同じである。整然と並んだ点(あるいは線)の集合体は色を薄く見せる効果しか引き出せない。
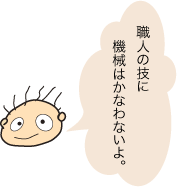
一方手造りの江戸小紋は、と言うと、離れて見ると全体に霞がかかったように見え、細いけれども点や線が感じられるのである。正確に彫っているつもりでも、それらの点や線の間隔は微妙にずれている。それは数ミクロン単位かも知れないが、顕微鏡ででも覗いてみれば、その誤差は充分に確認できるはずである。
その誤差とも言えないような誤差が、我々に手造りの良さを感じさせてくれるのである。完璧に近づこうとするけれども、完璧にはなれない人間の努力が我々の感性を和ませてくれるのである。
同じような事は他の染物にも言える。友禅染では、防染(色がにじみ出さないようにすること)の為に糊を使う。糸目と言われる細い糊の線で囲った中を染料で染める。柄の輪郭に沿って糊を入れていく作業も熟練職人の技である。これもまた、細く正確に一様な太さで引かなくてはならない。
しかし、最近は「型糸目」という技術が進歩して、糸目を一気に型で入れてしまう技術が有る。十年位前でもその技術はあったけれども、そのころの型で引かれた糸目は太く、とても見られたものではなかった。しかし、最近は技術が向上し、とても細い糸目を型で引かれるようになった。

それでも、較べてみれば手描きの物には叶わない。型糸目の方が、その太さは細く一様では有るけれども、どこかが違う。手で糸目を引いた友禅は、江戸小紋と同じようにいくらかの誤差が我々の目を楽しませてくれる。
きものに限らず、そのような例は他にも沢山有る。機械編みのニットと手編みのニットもその例である。機械編みのセーターは目が細く、きれいに編まれているが、目が粗く、少々編み方が下手とも言える物でも手編みのセーターの方が暖か味を感じる。恋人が心を込めて編んでくれた、とか母親が丹精込めて編んでくれたというような特別な思い入れが有るものも有るかも知れないが、それなくしても手編みのニットは暖かさを感じさせてくれる。
最近は技術の進歩で、完璧な物にお目にかかるようになった。車を買えば、髪の毛一本程の傷もないピカピカの新車が届けられる。八百屋の店頭では、全て同じ大きさ、色の果物や野菜が行儀良く並んでいる。現代人の目には完璧な物以外は全て難物、欠陥商品という意識が育っているように思える。
浴衣を着る人はめっきり減って、昔と較べて生産量、販売量ともに減っているれども、若い人の中には一時的なブームに乗って浴衣を求める人もいる。

浴衣は、もともと職人が型で染めたものだった。しかし、最近はプリント物が増えている。その理由はいくつか有るけれども、第一に安価にできること。第二にどんな色でも出せること。第三に細い柄でも完璧に染め上げることができる事などである。
最近の若い人達の浴衣にはキャラクター物という現代感覚の色や柄が多い。浴衣のデザイナーと言われる人達が作るどのような色や柄でも完璧に染められるのである。昔ながらの本型染ではそう言うわけには行かない。どんな色でも出せるわけではないし、細い柄は絹物を染めるのとは異なり、染料が泣いて(滲んで)しまう。
浴衣は2尺4~5寸(90~94センチ)の型を用いて、折り重ねた木綿生地を型ではさみ染料を注ぐ、「注染」と呼ばれる染色法で染められる。これも手による職人技で、どうしても若干の泣き(滲み)は免れない。
余りに泣きがひどい物は、検反の際にはねられるが、約5パーセントは難物としてはねられるという。運良く検反を免れた反物も、鵜の目鷹の目で見れば、いくらかの泣きは見つけることができる。最近はこういった技術の誤差とも言えるものも、消費者には難物と見る向きが有る。
正確無比に染められたプリントの浴衣を見慣れた人達の目には、技術の誤差は難物に映るらしい。そういった話を浴衣の染屋さんに話をすると、
「そこまで言われたら、我々は仕事になりませんよ。」
と苦笑する。
綿反に限らず、こういった問題は絹物にも起きている。きものの材料とも言える白生地にも生地難というものがある。白生地には、主に縮緬(ちりめん)と羽二重がある。私も縮緬の産地である丹後の工場見学に行ったことがあった。
工場内では機織り機械がガチャガチャと音をたてながら白生地を織っている。検査に見回っている人が生地難を見つけると、直ちに機械を止め、すでに織られた横糸を解き、難の有る所まで戻り難を除く。白生地の難は、異物が混入して織り込まれたりしたときに起こる事が多い。
織り上がった縮緬生地は精錬されて糊を抜き、真っ白な輝く白生地となる。
しかし、こうして出来上がった白生地でも、厳しい検査を通るとB反と言われる難物が相当数出てしまう。B反は安い値段でB反市場に卸される。ここまでは機屋の品質管理の責任によるものである。B反をいかに減らすかは企業努力にかかっている。しかし、問題はこの後である。
白生地は買継問屋を経て染屋に卸される。染屋で染められた白生地の中には、染められることによっ生地難が浮き出てくる事が有る。絹の生地はデリケートで、検反の段階では難がなくとも、生地の若干の性質の違いが染に影響するらしい。
丹後の縮緬研究所を訪れたとき、縦糸を左右半分ずつ日本製と中国製の繭で織った白生地を見せられた。糸の性質の違いによって、同じ染料で染めても左右染め分けられたようになっていた。
そういったケースの染難は染屋では容認できず、染上がった反物を白生地屋に返品するという。染屋にしてみれば、難の原因は白生地に有るのだから機屋に返品するのは道理だが、この場合染価を上乗せして返品される。白生地屋にしてみればたまったものではないが、染難の因果関係をたどっていけば、このようなこともうなずけなくもない。
力の有る白生地問屋は、返品を拒否する事も有り、染屋と白生地屋の板挟みとなった問屋がかぶる、といったケースもあるらしいが、力のない白生地屋は、やむなく返品(というよりも賠償)を受け入れざるを得ない。
ただでさえ中国やその他の外国産に押されている白生地業界である。さぞ大変だろうと思うけれども、私が心配してもどうなることでもない。染屋が難を容認して流せば、問屋、小売店を経て、結局消費者に難を指摘され又染屋に戻ってくることになる。このような染難はどこまで許容されるものなのだろうか。
御客様が2~30年前のきものを持ち込み、仕立て替えを頼まれることが有る。母親が嫁に来た時のきものを娘の支度に、という極普通のことである。時には戦前のきものにもお目にかかる。
私にとっては、昔の生きたきものを見る良い機会である。昔の染物には今の染物とは違った趣が有る。現在の友禅ほど細かに染められてはいないけれども、大胆に染められた柄は実に生き生きとしている。
染められて仕立てられ、数十年経たきものなので、しみや黄ばみも見られるけれども、染めそのものにも当初から色が微妙に違っていたであろうと思われる物や、色がはみ出したりしている物も見られる。
そして、何よりも感じるのは、絵羽柄がきれいに合っていない事である。絵羽柄は縫目を越えて一つの柄を創るものである。脇縫いや背縫いにまたがる柄は縫目を感じさせないように染め、そして仕立てなければならない。
現在の感覚では、よほど身幅を広くとらなければならない人(太った人)でなければ、仕立ての工夫で極力絵羽柄が合うように仕立てられる。身幅の広い人でも、柄を足して何とか柄が合うようにすることさえある。しかし、昔仕立てられたきものには、絵羽柄が合わないものが少なくないのである。
「良くこんなもので通ったものだな」 と思ってしまうが、それは現代人の感覚なのだろう。昔の人の絵羽柄に対する感覚の許容範囲内であったことは間違いない。現代から昔の人を見れば、「いいかげん」「適当」と見えるかも知れない。しかし、見方を換えれば、昔の人は正確な物づくりよりも、染物の本当の良さを大切にしていたのではないだろうか。
正確な物づくりを目指してきた結果、造りの正確さにばかり気がとられ、手造りの良さはそっちのけというのが現代の感覚ではないだろうかとも思う。
手造りの江戸小紋を見て、そのわずかな誤差を指摘し「これは難物だ」と言う人が現れてもおかしくなさそうである。

