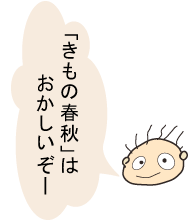全日本きもの研究会 続きもの春秋
18. おわりに(きもの春秋批判)
きもの業界に入って二十年余り、業界の矛盾や思うところを徒然に書いてきたのが『きもの春秋』である。自分の生業の記録として書いてきたつもりだったけれども、はからずも多くの人に読んでいただける機会を持てたのは私にとって幸いだった。筆無精で通ってきた私の随筆?が他人の目に触れるなど考えもしないことだった。それ程多くの人に読んでもらう事を前提に書き始めたわけではなかったので、内容には知識不足故の誤りや自分の勝手な思い込み等、読まれた方は多々批判を覚えたことと思う。読んでいただいた方より丁重な励ましの言葉や誤りの御指摘を頂戴し、私はこれに過ぐる幸せはないと思っている。
思うに人間の思考は、どんな人であれ自己中心に働くことは論を待たない。自己中心の考えであればこそ個人の思考と言えるのだけれども、人はそれぞれの知識や経験を基に思考を組み立てていく。従って個人の意見は自己中心的になるのは免れえない。しかし、時としては度を越えた論理の展開を人間はするものである。
己の知識と経験とを積み上げながら論理を展開する分には、その考えがいかに浅薄な知識と経験によるものであっても個人の意見として十分に尊重すべきであるが、いきおい思考の本末転倒とも言うべき、手段と目的がひっくり返る事が往々にしてあるものである。
すなわち、自分の勝手な思い込みによる結論を先に考え、論理の展開に必要な事実はそれを裏づけるのに都合のよい物だけを取捨選択してしまうのである。かかる思考法は政治やマスコミの世界によく見られる。自分の主張したいこと報道したいことに固執するあまり、自分に都合の悪い事実や証拠には目を背けてしまうのである。三面記事の取材ではあらかじめ自分が決めつけた結果の裏を取るだけの取材、私はそう言う取材を何度も見て知っている。その結果、住民不在の政治、始めから結論が創られている取材報道がなされるのである。
日本の政治や全国に流される報道がそうなのだから、まして私などその傾向が多分にあると考えたほうが早いだろう。
私は思考を続けたときに、ふと立ち止まって自分を批判してみることにしている。自分が自分にとって心地よい結論を出せば出すほど論理の展開は己の経験と知識を越え、時としては結論に違う事実を見過ごしている場合が少なくないのである。自分自身が構築した論理の展開を冷静に考え直して、むしろ批判的な目で再考察すれば、真理を探究する振子は中庸に戻ると思えるのである。
そんな訳で自分自身が『きもの春秋』を批判してみなければならないと思っている。
『きもの春秋』並びに『続きもの春秋』を御読みいただいてどのように感じただろうか。私はきものに関して相当に保守的、反動的と思われたかも知れない。本文の中でも触れたけれども、私はそれ程自分が保守的だとは思ってはいない。しかし、そう思われてもしかたのない部分もあるのは否めない。
私の考えが批判される第一の論点は、現在のきものが乱れているか否かである。
きものに限らず衣装の形や習慣は時々刻々と変わるものである。それは私もその通りだと思っている。それまでの常識に違うものを全て否定するのは間違っている。
「ゆかたの比翼」「紬の訪問着」「紬の留袖」について私ははっきりと否定してきた。私の主張は単純明解である。過去の伝統を知らず、踏まえずに変化を求めるのは正当な改革ではないとの立場をとってきた。はたして世の中の変化、文化の変遷は、常にそれまでの伝統を踏まえたものだったのだろうか。
現代の若者が唐突とも言えるようなきもの文化を求めているのは、長い歴史の中にあって極有り得べきものなのだろうか。もっと平たく言えば、文化の変遷などというものは何かにと講釈するものではなく、その時々の人々の好みと嗜好に合わせて変化するのが正当な発展なのだろうか。自然の成すがままに任せておけば、それまでの文化が否定されようが文化は有り得べき方向へと進むのだろうか。私が何を叫んだとて、どんな形であれ百年後には百年後のきものの文化は存在するだろうし、連続的に連還する歴史の中では時々刻々と修正されながら変化していくのだから決して人々の好みを無視した物になってはいないだろう。
スペイン、カタルーニャの生んだアントニオ・ガウディという天才建築家がいる。バルセロナに点在する彼の作品は未完の聖家族教会をはじめ、(見る人によっては)奇々怪々な建築物である。気違いが創った建築のようにも、未来を先取りした建築のようにも見える。そのアントニオ・ガウディが次のような言葉を残している。
「ルネサンスはゴシック建築の正当な発展を阻んだ。」
中世の西洋建築は教会建築が主流となり、ビザンツ様式、ロマネスク様式、ゴシック建築を生んだ。中世の人々は人間ではなく神中心の観念をもって建築物を創ったが、十五世紀に興ったルネサンスの人間中心の世界観はゴシック建築の発展を阻んだと言うわけである。敬虔なカトリック教徒だったガウディはゴシック建築の正当な発展を願って彼流のネオ・ゴシックとも言うべき建築を創造した。ガウディの建築がはたしてゴシック建築の発展すべき姿なのか、あるいは進むべき選択肢の一つであったのかは私は専門家ではないので分からない。しかし、彼はそれまでの建築様式を全て知り尽くした上で次世代のあるべき建築を世に問うたのは間違いない。
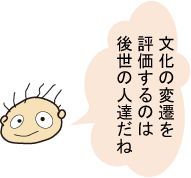
一方、ゴシック建築の発展を阻んだとされるルネサンスはどうだろう。神中心の暗雲たちこめる(現代人からみれば)中世に突如として興ったルネサンスはそれまでの中世の価値観を真向から否定するものであったけれども、唐突な思いつきで生まれたものではなかった。遠い昔、ギリシャからローマという長い時間をかけて築かれた文化を見直し、それを踏まえて興ったものである。正当な文化はきまぐれで興るものではなく、そこには人間の深い歴史に裏打ちされているように思えるのである。
現代の若者の感覚は洋服の影響を強く受けている。ガウディの言葉を借りれば、
「洋服は、きもの文化の正当な発展を阻んだ。」
ということになるだろうか。
私が否定している命題は、はたして歴史的価値観を含んでいるかどうかと言うことになろうかと思う。御判断は読者に仰ぎたい。
私が批判される第二の論点は、きものの善し悪しについては私の極個人的な好みの域を出ていないのではないかという事にある。
「若い女性には、伝統的な明るい色のきものがよく似合う」
「男性の普段着に白足袋は似合わない」
など、それらは私個人の趣味であって、万人に押しつけるべきものではないと言うことである。
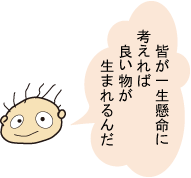
先に記したように、個人の主張はその人の知識と経験、そして好みによって形成される。私は浅薄ながら過去のきものについての知識と経験を踏まえて自分の好みに言及しているつもりである。きものの将来を考える人達の好みが一致するとは限らない。むしろ好みは十人十色だろうと思う。そういった人達が好みを主張し合い、きものの将来を考えることは有用である。
紬の訪問着や留袖を本気で考えている人達はそれなりの信念あっての事とと思う。そこからきものの将来は生まれてくるのである。確固たる信念をもった好みは次世代を生む原動力となるだろうから。
第三の論点は、私が呉服業界、実際に呉服を商う立場にいながら商売の視点を離れているのではないかとの批判である。
私は業界の内側から業界の事について論じてきたつもりだし、傍観者的な立場に立っているつもりもない。しかし、商売の第一目的が金儲け(利益を出すこと)とするならば、『きもの春秋』は評論に過ぎないのではないかという点である。
不況下の昨今、呉服業も御多分に漏れずに低迷している。低迷で終われば良いが、衰退しているようにも思える。業界の人間は皆売上を確保することに汲々としている。私の店とて例外ではなく、来年の商売像さえ掴めないでいる有り様である。そんな中できものの今後のあり方を云々するのは、まじめに商売をしていないのではないかと思われるのである。
「ゆかたの比翼」も「紬の留袖」も売上を創るための商売の方策であり、売れることが全てに優先される。そういう考え方から見れば、売れているものを批判する必要はまったくないのである。さらに歴史的にまじめに反論していただければ、きもの文化とて商売によって支えられてきたのである。きものを商う者が売れるものを売ってきた故に現代のきものがある。現在の商いの形もきものがより売れる方向へと考えれば、きものは決して悪い方向へは行かないとも考えられる。
きものが売れなくなれば成るほど、いかにしてきものを売るかに重点が置かれてくる。巷では、一人で年間一億円売るにはどうするか、の類のセミナーが話題を呼んでいる。一人で年商一億など誰でもできることではなく常軌を逸しているように思えるけれども、その立場の人から見れば、きものの将来云々など机上の空論に等しいのだろう。
しかし、売上至上主義に走った時、きものはきものではなく商売の媒体でしかなくなってしまうのである。「ゆかたの比翼」や「紬の絵羽物」など、『新商品』について本質的な性質が業界で議論されたことがあっただろうか。それらを店頭に並べる判断は、売れるか売れないかだけで判断されてきたように思える。
商品が売れるか売れないかは、卸屋、小売屋ともに重大関心事である。しかし、商品そのものの持つ性質については全く議論されなかったと言って良い。(「業界が怠ってきたこと」参照)
きもの業界の発展を、ただ売上の増進、生産量の拡大だけで考えるのならば、私はそれをはっきりと否定したいと思う。需要の拡大、量的拡大をもって業界が隆盛であるという考え方は業界の足元を掬う原因となりかねない。いままで呉服業界は需要(本質的な需要ではなくて販売量)の拡大を図り突き進んできた。しかし、需要が本質的な需要なのかどうかを考えることなく、売り方の工夫の競争に翻弄され、本質的な需要の創造追求には至らなかったと思える。
本質的(必然的)な需要であれば、不況で売上が減少しようとも1~2割の減少で留まったかも知れない。しかし、二十年足らずで五割の減少を見ている呉服業界は何かが誤っていたと言わざるを得ない。
売り方を工夫してきたからこそ今まで需要が換気されたのだと言う意見もあるかも知れない。あの手この手の商法がなければ遠の昔に呉服の需要は萎んでいただろうことは私もその通りだと思う。しかし、今よりは遥かに健全な形でいられただろう。水脹れの業界は一度ことが起これば一気に萎んでしまう。不動産業始め多くの業界がバブルの崩壊と共にたどった運命を見れば明らかである。
資本主義の経済は経済環境の急激な変化には脆弱である。円相場が上がったにせよ下がったにせよ急激な変化は日本経済に大きな痛手となるのと同じように、呉服の需要の急激な減少は呉服業界を崩壊へと導くものである。急激な変化は健全な淘汰には結びつかず業界の浄化にはつながらない。業界にとって是非とも必要な熟練技術者を振り落とし、築き上げてきた伝統文化の破壊につながるのである。

業界が今後どのような形で残るべきなのか、私にははっきりとした答えは出せないけれども、問題を提起したつもりである。売上至上とする考えもまた一つの考え方であり、大いに議論されるべきと思う。