全日本きもの研究会 続きもの春秋
13. 紬の留袖
先日問屋さんが訪ねてきた。いわゆる新規開拓という問屋の出張員の訪問である。私も京都の問屋にいた時分には新規の小売店を訪問した(させられた)ものだった。小売店の主人にもいろいろなタイプがある。新規の問屋の出張員でも時間があれば気軽に相手をして話を聞いてくれる人。新規の問屋と言っただけで、「間に合ってます」という態度で鼻にも掛けない人など様々である。
私は新規の問屋が訪ねてくれば、とりあえず話を聞くことにしている。自分が問屋時代に経験した出張員の立場に同情してではない。問屋の情報は小売店にとって得難い情報である。最近は特に染屋、機屋が廃業して商品が昔のように豊富に出回らなくなってきている。昔は注文をすればいくらでも商品が届いたけれども最近は思うように商品を集めるのが難しくなっている。今、どこの問屋がどんな商品を扱っているのか、そしてその問屋はどのくらい力があるのかを把握しておかければこれからの商売は難しいと思うのである。
「小売屋は神様」の如く振舞い商品を集めていた時代は終わりを告げる。そして、小売店からアンテナを延ばして情報を集めることが必要なのである。
さて、今回訪ねてきたのは、さる地方問屋だった。話は結城紬の販売企画。語りべを招いて客を集めようと言う今流行りの企画だった。その手の企画は当店では得意ではない。当社では乗れない企画だと言ったが話は進んだ。出張員いわく、
「この手の企画は他の問屋でもありますが、当社では結城紬の留袖を扱っています。これがよく売れています。」
『結城紬の留袖』と聞いてどう思うだろうか。従来(ここ数十年)の感覚で言えば、紬は普段着、礼装には用いないというのが通説であり、ほとんどの小売屋はそのように消費者に説明してきたはずである。しかし、ここ十年位の間に紬の訪問着や大島紬の振袖までもが登場し、紬を晴れ着として扱う動きがあるのもまた否定しがたい事実である。さすがに第一礼装である黒留袖を紬地で創ったという話はまだ聞いたことはなかった。
その出張員は自分の会社の戦略商品とばかりにパンフレットを開いて説明した。写真で見るその黒留袖は石持で、三十六歌撰か何かの人形柄が染めてあった。その出張員も雄弁で(販売マニュアルなのかもしれないが)説明を始めた。
次は私とその出張員との会話である。
「ええ!、結城紬の留袖ですか?。」
私が言うと、待ってましたとばかり応えた。
「紬の留袖と言うと違和感をもたれるかもしれません。私も初めはそうでした。しかし、ここ数年きものを着る人の価値観も変わってきまして、紬の晴れ着も受け入れるようになっています。」
「しかし、紬の晴れ着というのは・・・。」
「今のきものの源流は昭和になってからです。きものの常識も変わってきます。これからは紬の留袖も着るようになります。私どもでは現にこの留袖が良く売れています。」
「売れているのではなくて、売っているんじゃないですか。」
「はい、確かにそういう面もありますが、結城紬の留袖は明治時代に実際にあったのです。私どもの語りべはそこのところを良くお話してお客様に納得して買っていただいています。」
「明治時代に紬の留袖ですか?。紬の喪服じゃないんですか。紬の喪服は私も知っています。」
「ええ、喪服もありますが、留袖があったんです。結城紬の。」
「それはどこでですか。石毛地方ですか。」
「いいえ、違います。」
「全国的に紬の留袖があったのですか。」
「いや、長野県のある地方です。ある人が京都で染めさせたものだそうです。」
「それはその人が個人的に染めた物ではないのですか。それともその地方で紬の留袖が一般に着られていたのですか。」
「それは分かりませんが、何人か複数の人が持っていたということです。」
出張員は得々と説明を続けたが、私は
「私はお客様に結婚式で紬の留袖を着てくださいとはとても言えません。私の店には合わない商品です。」
私はきっぱりと断ったつもりだったけれども、その出張員はさらに続けた。
「結城では年々織る人も糸を紡ぐ人も減ってきて生産量も激減しています。(パンフレットを指さして)従来はこのような無形文化財の絣が織られてきました。しかし、着る人も少なくなり、それだけでは食っていけなくなっています。こういった染め物も作らなくてはならないのです。」
「十年経ったら来てみてください。十年もすれば、世の中も私の考えも変わっているかも知れませんから。」
出張員は私の言葉に納得(?)して帰った。
翌日。昔から出入りしている問屋さんが来たのでその話をしてみた。その問屋さんは三十年以上も私の店に出入りし、いまでは一人で商いをしている。当社と長年付き合っていると言うこともあるだろうけれども、
「ええっ!、結城紬の留袖?、とうとうそんなものまで出ましたか。」
驚きともあきれともつかない言葉だった。従来の常識を建て前とする者には紬の留袖などとても受け入れられない。しかし、一方で紬は晴れ着で構わないと主張している人がいることも知っている。
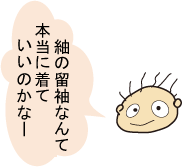
結城紬の黒留袖というのは本当に売れているのだろうか。そして、それはこれから着物の文化の一つとして市民権を得ていくのだろうか。紬の留袖云々の問題はひとりその是非を問うだけの問題ではなく着物文化は今後どのように変遷していくべきかという着物文化、着物業界生き残りのかかった問題をも含んでいるように思われる。
今の着物の様式が整ったのは、その出張員が言うまでもなくそれほど昔のことではない。江戸時代に今のような着物の形式はなかった。
現代から遡って考えれば、羽織はつい最近(二十年程前)まで着られていたが最近は何故か着ないという。色無地に黒の羽織は私が子供の頃には入卒時の母親の制服だったが今はほとんど着られていない。付下という着物の形式ができたのは戦後である。そして、その少し前、戦前には縞の御召に羽織というのが女性の正装だったという。名古屋帯という形式ができたのは大正時代に起こった服装改良運動の成果の一つである。その頃の袋帯は現在とは違った結び方をしていた。
さらに遡れば、着物の形や帯の結び方は現代とは全く異なっていた。辻が花が全盛だった桃山時代、辻が花染で染められた多彩な柄模様は男性の着物として創られていた。現在、男性が柄物色物(多色の)の着物を着ることはほとんどない。染め物ではせいぜい細い柄の地味な江戸小紋、大きな柄の小紋や絵羽物を着るとすれば役者か、南春夫氏等の芸能人のたぐいであろう。
そういう目で見れば、着物の文化も目まぐるしく変わってきたと言える。そういう意味で結城紬の黒留袖はどのように捉えるべきなのだろう。着物文化の次代への正当な変遷の一過程と考えるべきなのだろうか。
私の店に黒留袖を売り込みに来た出張員の話を要約すれば次のようになる。
1.結城紬の黒留袖は今売れている。
2.きものの常識は時々刻々変わるものである。
3.明治時代には結城紬の黒留袖が作られていた。
4.結城では染め物に頼らなければやっていけない。
以上のような理由で結城紬の留袖を扱ってほしいということなのだろう。
「本当にそんなものが売れているのか。」
「明治時代にそんなものが本当に有ったのか。」
など疑えばきりがないので、ここでは全て鵜呑みにして話を進める。
1.については前述の通り、「売れている」のではなく「売っている」側面が強いように思われる。現在の呉服業界において売れているという市況が想定できるだろうか。まして黒留袖という高額品市場で「売れている」と言われる程の市況があるのだろうか。企画販売を行ない、語りべに紬の留袖の正当性を語らせ売っているのではないだろうか。結果的に売れた事実をもって「売れている」とするならばそれも良いかも知れないが。
2.については私は否定するものではない。私も着物の常識は今後も変わっていくものと思っている。
3.については、私は初耳なので事実を確認しなければ何とも言えない。しかし、洋服がほとんど無かった時代に紬の(普段着の)留袖が作られたと言うのはありそうな話である。
喪服は、最近は精華、縮緬が多いが、昔は羽二重地がほとんどだった。今でも羽二重地を指定してくる人もいる。そして、その当時は紬の喪服も作られていたと言う。紬の(普段着の)喪服は、それで葬式に列席したわけではなくて手伝い着用の喪服だったという。昔、葬式といえば近所の人が集まり、炊き出しやらその他雑事を手伝っていた。その雑事をこなすためにあったのが紬の喪服である。今の洋服の感覚で言えば黒のエプロン、黒のサロン前掛けと言ったところだろうか。今でこそ葬式に必要なのは礼装だけだけれども、普段着の喪服というのは当時必要欠くべからざるものだったのである。
紬の留袖はそれと全く同じに普段着の留袖として結城紬の留袖が作られたとは考えにくいけれども、その当時の環境、すなわち洋服がほとんど無かった時分に何らかの理由で紬の留袖が作られたと考えられなくもない。あるいは縮緬生地が手に入らずにやむを得ず紬の留袖を作ったのかも知れない。
どちらにしても、全て和服でこなさなければならない環境にあって紬の留袖が作られたのだろうけれども、それが大手を振って礼装としてまかり通っていたとは私には思えないのである。
4.については、純粋に商売という目で見れば、新商品の開発というところだろう。他の理由が無くただ目新しい商品を市場に流すのであれば、従来の着物の文化との整合性を考える必要が有る。
上記のような前提において紬の留袖が今後日本文化として受け入れられるものなのかどうかを考えなければならない。
服装における常識の変化は日本の着物でも前述した通り頻繁に起こっている。それではその変化は 何が原動力となって起こったのだろうか。その因果関係が正当なものであれば、その変化はその後の文化として受容できるものだろうし、そうでなければ線香花火の如く一時の流行りで終わってしまうだろう。
一つの視点で捉えれば、変化は需要者の要求から起こったものなのか、それとも供給者が人為的に創ったものが拡がったものなのかを検証する必要がある。紬の黒留袖や訪問着は明らかに供給者が創ったものを消費者に押しつけているようにも思える。洋服の世界では供給者(メーカー・デザイナー)が提案した物を消費者が取捨選択し、その時々のトレンドが生まれている。消費者の支持を得たものはヒット商品としてもてはやされる。それは新しい文化を生み出す一つの方法であると思う。
しかし、現在の呉服業界の場合、洋服に比べて(数において)需要は極端に少なく、消費者に流される情報もまたはるかに少ない。そんな環境にあって供給者から与えられた商品を正しく取捨選択できるものかどうかは甚だ疑問である。つんぼ桟敷に置かれた消費者が一つの情報を鵜呑みにしてしまう可能性は大きいと言える。その意味で呉服問屋、小売屋が消費者に対して正しい豊富な情報を流す義務を負っているはずである。そして、その情報をもとに消費者が判断すれば業界はおのずと良い方向へ進むものと私は確信している。
紬の留袖について、結論から言えば私は反対である。次世代の着物文化とするには無理があるように思える。 もしも、紬の留袖や訪問着が、ただの販売促進の手段としての新商品開発の意図で創られたのだとしたら、それまでの常識を無視したものと言える。
それ以上にその正当性を主張する人もいる。
「昔、紬の留袖が作られていた。」
というのは前述の如く例外的だったろうと思うし、また、
「最近は着物を着る機会が少なく、着物を着る事自体が晴の時なので、紬は晴着として着ても構わない。」
という意見も聞く。その考えに従えば、留袖であろうと訪問着、果ては振袖、打掛であろうと紬で創るのは許される事になる。『着物は全て晴着』ということになろう。
しかし、私はその考えは日本の文化を全て否定するものだと思う。確かに着物の需要は減り、着物を着る機会は少なくなっている。普段着物を着ない人が紬であっても着物を着れば、
「今日は何かあるのですか。」
と問われる昨今である。『着物を着るのは特殊な時』というのもあながち嘘ではない。しかし、だからといって着物を全て晴着とするには無理が有る。
いくら呉服の需要が小さくなろうと、着る人が少なくなろうと、着物の文化はあくまでも一つの体系をなしている。いくら小さな体系であろうと、そこにはピンが有りキリがあるのである。それは凝縮された日本文化と言えるかも知れない。
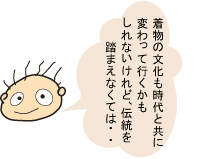
1000人を超えるマンモス小学校であろうと、全校児童わずか30人程度の郡部の小学校であろうと、そこには校長先生がいて教職員がいて養護教員、技能技師(昔で言う用務員)が同じようにいるのである。それは省略できることではなく、数が少なかろうと校長先生や技能技師を省くことはできない。
今よりもさらに呉服の需要が細り、日本文化の標本の様になろうとも、着物それぞれの役割は厳然として保たれなければならない。それは日本文化の誇りとする物ではないだろうか。
オリンピックやその他世界の人々が集う場所で、アジアやアフリカのいわゆる経済的に貧しい国の代表が自国の民族衣装を誇らしげに着て参加しているのは衆知の通りである。先進国と言われる国々の人は皆揃って最新のファッションに身を包み参加している。自国の文化を否定している訳ではないだろうが、先進国と言われる国程自国の文化を外に出そうとしないのは何故だろうか。貧しいと言われている国々でも今は始終民族衣装を身に纏ってはいない。普段は洋服を着ている人達でも対外的には誇らしげに自国の民族衣装をアピールしている姿はすばらしいと思う。
どこの国の民族衣装でも晴着があり普段着がある。どんなに自国の文化が西洋化しようとも、彼らは普段着の民族衣装で世界の檜舞台に立つことはないだろう。紬を晴着とするのは自国の文化を否定することに他ならない。
服装に限らず、それまでの常識や様式が変わるというのは歴史的に度々有ったし、私はそれを否定するものではない。問題はそれまでの文化を踏まえて次代に受け継ぐことができるかどうかである。例えば室町時代末期より桃山にかけて価値観の大きな変化があった。『わびさび』の登場である。
利休によって『わびさび』が確立されるまでは仏教の色である金や銀に対する価値観はそれ以後とは大きく異にしていた。金や銀を外に出すことをはばかるようになったのは桃山以降である。
それまでは金は仏の象徴として扱われてきた。足利義満が建てた鹿苑寺金閣。豊臣秀吉が造った黄金の茶室も今日とは違った価値観のもとに創られていた。秀吉の茶室では茶筅と茶杓以外は全て純金の茶道具が揃えられていた。彼が農民出身であった事と相まって、成金の象徴のように今日の人々には思われるかも知れないが、当時としては時代の最高の物、最先端の物の意味を持っていたのだろう。
それまでの価値観を持つ秀吉と『わびさび』を奉ずる利休との軋轢が利休切腹という悲劇を呼んだのかもしれない。以後、『わびさび』は日本の文化の真髄をなしていく。それは権力者が押しつけたものでもなく、利休が利権にかられて広めようとしたものでもない。日本人が自ら選択したものである。
さて、そういう観点からみれば、紬の留袖は日本人に受け入れられていくのだろうか。
日本の文化は日本人自身が決めるものである。誰が否定しようと肯定しようと押しつけられるものではない。日本人が正しく日本文化を導いていくには過去の文化を正しく理解していくことがぜひとも必要と思えるのである。
選択は消費者に任せるとして、小売店はきものの知識を正しく紹介することが是非とも必要である。
関連記事
「続きもの春秋 3. 紬の絵羽(訪問着)について」
「続続きもの春秋 5. 呉服屋は文化の創造者になりえるか」

