全日本きもの研究会 続きもの春秋
17. 続 和服の危機(男物胴裏について)
『きもの春秋』の中で、和服の危機について触れた。和服の危機はきものを着る人が少なくなる以前に、きものの仕立てや着付けに必要な小物や付属品がなくなってしまうというのがその要旨だった。そして、今それを裏づけるような事が次々と起こっている。
先日、三河の綿反屋さんがやってきた。知多木綿の産地である三河では昔から綿織物が盛んである。綿反といっても、普段にきものを着る人が少なくなった今、綿の反物を扱うのではなく、主に綿の帯芯、晒、その他綿製品が主である。私の所に来るその三河の綿反屋さんも『帯芯の○○』という名で通っている。
今では綿反屋は呉服業界では陽の当たらない(と言っては申し訳ないが)問屋である。しかし、そこで扱っている商品は帯芯をはじめ、新モス、背伏せ、黒八、晒など、きものにとってはなくてはならないものばかりである。そして、その問屋さんが扱う商品に男物の胴裏がある。その胴裏は細番手の綿の胴裏地で、表生地に合わせて色数が七~八色ある。私の店では男物の裏地にはほとんどそれを使っている。
女物の胴裏は通常正絹の羽二重を使う。戦前は若い人の胴裏は紅絹(もみ)という緋色に染められた羽二重を使っていた。男物の胴裏は羽二重を使う場合もあるが、私の店では綿の胴裏を使っている。
綿の男物の胴裏は金巾(カネキン、カナキン)と呼ぶのだと私は京都で教わっていた。もっともこれは、はっきりとした名称ではなく、私の周りにいた人達がそう呼んでいただけかもしれない。
せっかくなので綿の胴裏についてその出張員に聞いてみた。
「男物の胴裏は正式には何と言うのですか。」
その出張員はちょっと困った顔をして、
「う~ん、男物の胴裏は・・・、格別呼び名は無いな。」
「私は金巾と教えられましたが。」
「いや、金巾は正絹地の胴裏には使わん。いや、使えるとは思えん。」
「じゃあ、金巾というのは何なんですか。」
「金巾ちゅうのは、40番手の糸で織った広幅の織物の事と覚えとります。」
「40番手ですか。何に使った物ですか。」
「昔、綿のきものを着とった時に裏に使ったもんです。正絹の裏にはとても・・・。」
「お宅の胴裏は何番手の糸なんですか。」
「これは180番手です。100番手以上になりゃ、これが何番手かなんて手で触って分かるのは本当の職人さんだけです。反物を百反も重ねりゃはっきり分かりますが。ただ40番手の金巾は分かりますよ。ゴワゴワしますから。」
その出張員が言うように、180番手で織られた綿の胴裏は絹以上に薄く、すべすべとしている。私も何着かその胴裏を使ったきものを着ているが、実に着やすい。
さて、その出張員に抜けた色の胴裏を注文しようとすると、
「今までは東京の染屋に頼んでいたんですが、その染屋がやめちまってね。」
最近、廃業や倒産する染屋が後をたたず、別に珍しい話題ではなかった。
「それでどうするんですか。在庫はあるんですか。」
「いや~、それが京都の染屋に替えて染めさせたんですが、その染屋も年間二万反の注文がなけりゃ、勘定が合わんで、やめるって言うんですよ。」
「二万反ですか。そんなに捌けるもんですか。」
「まあ、うちの店じゃ二五○○反がやっとってところかね。他の問屋にも声を掛けちゃいるんだが、二万反なんか、とてもとても・・・。」
「じゃあ、どうなるんですか。うちも買い溜めした方がいいですか。」
「いや、まあうちじゃ相当数在庫置いてるで、しばらくは品切れっちゅうことはないです。」
そう言って色見本帳をめくりながら、その内の一色を指さして、
「この色はあるにはあるが、これはないですと言ってるんですよ。他の染屋にやらせたんだが、色は出ないし、整理も悪い。こんな胴裏売って文句言われるのもしゃくだからね。」
私は思わず笑ってしまった。
「頑固な寿司屋みたいですね。目の前にトロが有っても『今日はトロは無い』って言うような。」
私の言葉に苦笑するその出張員はもう五十年以上もこの仕事をして、綿反に関しては生き字引ともいえる人である。
「もっと他に良い染屋はないのですか。」
私が聞くと、少し寂しそうに言った。
「今時、いい工場なんかあらへん。」
和服の危機を象徴するような言葉だった。
きものの危機とは、ひとりきものを扱う人達の危機という以上の意味を持っている。言わば、日本人の生活、価値観の危機であると私は思っている。
世の中は昔に比べれば発達している。日本は経済的に高度成長を果たした。所得も上がり生活も向上しているはずである。科学技術の発達により、工場は機械化され、より良い製品が大量に安くできるようになったはずである。それなのに何故、『今時、いい工場なんかあらへん』なのか。大げさな言い方かも知れないが、この言葉は現代社会の病巣を的確に言い表しているように思う。
「染屋なんて捜せばたくさんあるように思えますが。」
「いや~あんた、そこいらの工場じゃ色はきちんと出せんし、だいたい満足な整理がでけへん。伸子を張って整理させれば、きちんとなるんだろうけれども、綿反なんかそれじゃとても採算が合わん。」
もしも、その出張員の言葉通りであれば、数年内に今使っている男物の胴裏は手に入らなくなる。手に入ったとしても、余り出来の良くない胴裏になるのだろう。綿の胴裏が入らなければ正絹の羽二重を使わざるを得ない。白の羽二重で気に入らなければ一枚づつ別染めして使うことになるだろう。そうなれば、きものは益々高価になり、着もの離れに拍車がかかるようにも思える。
高性能の自動車を作ることはできても綿反の整理ひとつ満足にできないのが現代社会らしい。
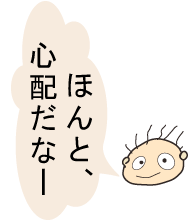
関連記事
「きもの春秋 20. 和服の危機」
「続続きもの春秋 24.呉服業界の危機」
「きもの春秋終論 Ⅵ-8.呉服屋がなくなる時」
「きもの春秋終論 Ⅵ-37.またまた呉服業界の危機(羽二重がなくなる)」

