全日本きもの研究会 続続きもの春秋
9. 工房訪問記『HANA工房』
『京都市上京区仁和寺街道千本東入ル』竹田しのぶさんのHANA工房の住所である。京都の住所は初めて訪れる者にとって分かり易い。京都の通りには全て名前が付いている。住居表示に丁目、番地はなく(本当はあるが住民が使っていない)東西南北の通りの名と、上ル、下ル、西入ル、東入ル、でたちどころに場所が分かってしまう。もちろん初めて訪れる者は全ての通りの名は分からないが、行き先の通り名を言えばタクシーはすぐに目的地に連れて行ってくれる。
HANA工房を訪れた日は雨だった。前日は曇っていたので、翌日までは降らないだろうという期待は裏切られて朝から雨が降っていた。宿からタクシーに乗り、
「仁和寺街道千本通り」
と運転手に言うと、

「はい、千本仁和寺街道ですね。」
と言って迷うことなく車を走らせた。千本通りが近くなり、
「京都の通りの名は全て分かるのですか。」
と訊くと、
「ええ、タクシー運転手ですから。」
と応えた運転手は女性だった。そして、
「仁和寺街道は西に入りますか。」
と訊かれ、
「いえ、東に入ってください。」
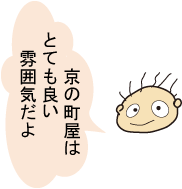
私の言葉に運転手は戸惑い、
「東ですか?、あそこは西へ入ることはあるのですが、東へは・・・。」
竹田さんに前もって訪れることを連絡した時に、
「ちょっと分かりずらいですから近くへ来たら電話ください。迎えに行きますから。」
という返事を頂戴していた。
仁和寺街道は千本通りと交差して東へ向うが二筋目の浄福寺通りで突き当たり途切れてしまう。仁和寺通りを東に入る人は少ないのだろう。一方通行かどうかも分からないので、
「千本仁和寺の角で結構です。」
と言ってタクシーを降りた。
千本通りは今では京都中心部の西よりにある通りだけれども、昔は平安京の中心街である朱雀大路にほぼ一致する。そして、千本通り仁和寺街道の交差点は大内裏の中にある。北へ二筋上れば平安京の北辺である一条通りが走っている。昔このあたりは通りなどなく、御所の建物に囲まれていた事だろう。雨傘をさして立っているこの場所から大極殿が見えたのかもしれないと思うと五月雨の降る千本通りに京都千年の歴史の重みを感じてしまう。しかし、現在の千本通りは昔の面影は微塵もない生活臭漂う街である。郊外ショッピングセンターやコンビニエンスストアといった無機的な買い物に慣らされている現代人には昔懐かしい、人情味あふれる商店街である。
竹田さんには電話をくれるように言われていたが、私も一度は京都市民だったという自負から電話をせずに仁和寺街道を東に入った。
車の通りの多い千本通りから東に入ると、そこはいわゆる西陣である。西陣の由来についてはすでに何度も述べているので割愛するが、そこは町屋が並ぶ静かな住宅街である。ここから東の次の大通りである堀川通りまでは西陣と呼ばれ、昔はそこここに機の音が響いていた。
やや下り坂の狭い仁和寺通りを歩いて行くと車が一台上って来た。さしていた傘を高く掲げて町屋の軒下に身を寄せてやり過ごした。車が去った後はまた静かな通りに戻る。傘を片手に一軒ずつ町屋の門標を見ながら歩いていった。『竹田』という門標の家があったけれども私は先に進んでいった。その家には『HANA工房』の看板は見当たらなかった。
「この辺りは竹田姓が多いのかも・・・。」
とも思った。途中町屋が途切れ駐車場やモダンな住宅もあった。しかし、どこにも『HANA工房』の看板は見当たらない。とうとう浄福寺通りの突き当たりまで来てしまった。
一軒一軒門標を確かめてきたので見落とすはずはない。
「やはり先程の竹田さんがHANA工房なのだろうか。」 そう思って竹田の門標の前まで戻った。どう見ても普通の町屋である。工房には見えない。
京都の町屋は一見只の住居のように見えても一歩入ると仕事場になっている処も多い。20年前に私が京都にいた当時も戸を開けると広い土間で湯のしをしていたり、染屋の仕事場であったりしたものだった。しかし、それにしても静かだった。 「ひょっとして間違いだろうか。」 と思いながら、おそるおそる格子戸に手を掛けた。
戸を開けると香の匂いがした。
「ごめんください。」
何度か言ってようやく返事が有った。
「こちら、竹田先生のHANA工房では・・・。」
薄暗い玄関に男性が出てきた。
「山形の結城屋ですが。」
その男性が竹田さんなのかどうかは分からなかったが丁重に迎えてくれた。
「どうぞ、お入りください。」
私は靴を脱いで奥の間に通された。床の間に香が焚かれ、座布団が対面するように敷かれている。私は床の間の座布団に座るように促された。
毎朝香を焚き染めているのか、あるいは私が訪問するので香を焚いてくていたのかは分からない。そして、床の間の接待。日本の文化の息づいている京都の町屋の生活に触れる思いがした。
竹田さんとの対話は呉服業界のことから先生の作品に及んだ。
竹田さんの作品は既にホームページで見てその素晴らしさは知っていた。「すくい」という織物で微妙な暈しを表現する精巧な手法は驚嘆に値するものだった。
「作品をお目に掛けましょう。ほとんど此処にありますから。」
部屋の隅には箱に入れた作品が積まれていた。無造作に箱に入れられて積まれた作品は妙に相応しく思えたのは何故だったろう。 先生の作品は全てすくいの訪問着である。すくいというのは複数の色糸を用いて柄の部分だけ左右に簸をとばして柄を織り出す織り方である。(『きもの博物館32、すくい帯』参照)
経糸を織機にかけて、柄の設計図である柄を描いた下描きを経糸の下にあてる。櫛のよう並んだ経糸を透かして下描き通りに色糸で柄を織り出して行く。すくい織は機織を生業とする者にとって最もやりがいのある仕事だと聞いたことがある。設計図はあるものの、経糸何本を掬うのかは織り手の主観にまかされる。同じ手機でも織り手の主観が最も繁栄される織物である。

竹田さんは柄の考案、色糸の選定も全て一人でこなしている。そして、その作品の特徴は暈しにある。染料を使って柄を暈すのは比較的容易である。加賀友禅でも暈し手法は多用されている。水彩絵の具で暈しを描くと思えば想像できるだろう。
しかし、暈しを織で出すのは容易ではない。色糸の数は限られている。明度の異なる色糸を順次織って行けば暈しになる。段階的に明度の異なる色糸100本で順次織って行けば見事な暈しになるはずである。しかし、明度が等間隔の糸100本を染めることも操ることもまず不可能である。
100本が可能だとしても、一枚の訪問着には数色の色が使われるので、数百本の色糸を染めて操らなければならない。・・・不可能である。
竹田さんは数本の糸を使って見事な暈しを織り出している。次のような手法である。
暈す色の明度が異なる糸を3~5本染める。色糸はもちろん別染である。濃い色から順に????と番号を付けて暈しをかける部分を四つのブロックに分ける。初め一番濃い?の糸で織り始める。そして5本に1本?を織り込み、さらに4本に1本、3本に1本というように?の糸を減らし、?と?の色が1本に1本となって、今度は?と?の色が逆転して、?の色が2本に1本?を織り込み、さらに3本に1本、4本に1本、5本に1本と織って行きます。一番目のブロックが終わるところで?の糸の代わりに?の糸が入ってくる。同じようにして四番目のブロックでは?と?の糸を使い、最後は?の糸のみで終わる。
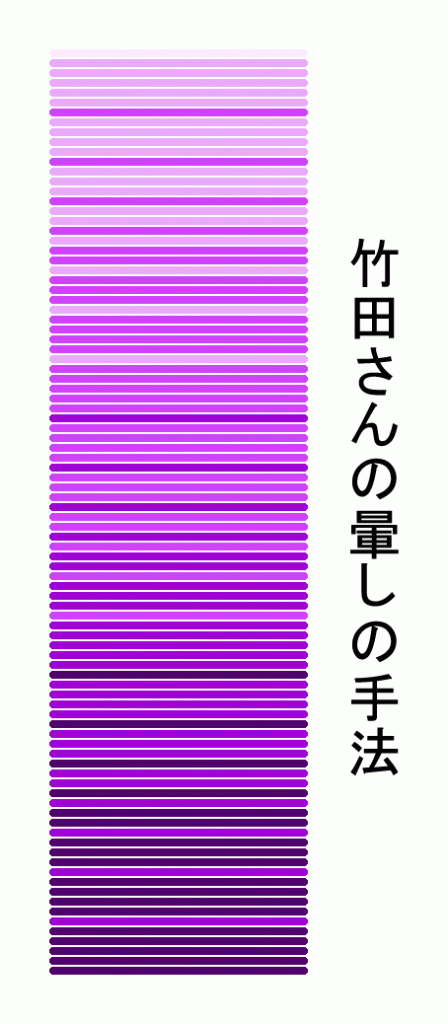
暈しの仕組みを口で言うのは容易い。上記の方法で織れば暈しを織る事はできる。しかし、暈しは連続的に、数学的に言えば線形または二次曲線に仕上げなくてはならない。素人が織れば、いわばデコボコの暈しになってしまう。さらに、竹田さんは玉糸にこだわり、全て玉糸を用いている。
玉糸というのは、二つの蚕が一緒に繭を造った時にできる糸で、二本の繊維が絡み合っているために、紬糸のような節ができて太さも生糸のように均一ではない。昔は屑糸として価値が低かったけども最近はその希少性と風合いが珍重され価格も高騰している。
暈しを織るには進度を計算しなければ暈しはデコボコになってしまう。巾が狭ければ制限された緯糸で暈しを表現しなければならない。玉糸は均質でないために織る進度は計算できない。経験に頼るほかないのである。
「1センチ織るのに緯糸は何本通すのですか。」
誰でもそう疑問に思うだろう。私は質問してみた。
「いや・・・、それは・・・、口では言えませんよ。」
竹田さんの応えである。竹田さんの頭の中では1センチに何本という定量的な判断は存在しないらしい。いや、定量的な判断では連続的な暈しは織り出せないのかもしれない。
織りあがったすくいの暈しは、近くから目を凝らして見れば数本の色糸が織り込まれているのが分かる。しかし、離れて見れば、あたかも染料で暈されたように見事に暈しが表現されている。
竹田さんは作品のほとんどを自宅に所有している。
「作品を売るつもりはないのですか。」
「いいえ、私も生活がかかっていますし、売らなければ食べて行けませんから。だけど、私のきものは手間がかかっていますので高いですからそうそうは売れません。」
道理である。いくら工芸作家と言えども作品を創るだけで生活はできない。竹田さんは他に織機を持って織屋の仕事もしているのでなんとか食べてはいけるという。しかし、今時御多分に漏れず西陣は景気が悪い。
すばらしい作品を生み出す工芸作家、といえばどんなにか満ち足りた生活をしているのだろうと誰しも思う。マスコミに登場するような一握りの作家を見ているとそう思ってもしょうがないかもしれない。しかし、
「良い仕事をすることと裕福になることは別物だ。」
と常々私は思っているつもりだが、それを目の当たりにしたように思えた。
「仕事は並行して行いますので、一枚の訪問着を幾日で仕上げられるのかはっきりとはいえませんが、仮に一月に一枚織り上げて売ったとしても、とても暮らして行けるものではありませんよ。」
私は商売に来た訳ではなかったし、余り銭金の話をするつもりはなかったが、その話を聞いていったいいくらぐらいで売れば良いのか聞いてみた。竹田さんの提示した金額は高い物ではなかった。きものの事を知らない人や竹田さんの仕事の価値を知らない人が聞けば高いと思うかもしれない。しかし、私の経験から言って決して高くはなかった。否、むしろそんなに安くて良いのかと思うくらいだった。もしも、きらびやかな展示会にでも出品されれば、その2~3倍の値がついてもおかしくはなかった。
「問屋とは付き合わないのですか。」
「ええ、一度地方問屋が話を持ちかけてきたことはあったのですが・・・。」
流通について多くは語らなかったが、私は竹田さんの気持が良く分かるような気がした。私が思っている今日の業界の問題がそこにあるように思えた。
作家や職人は何を思って作品を創っているのだろうか。きものの作家である以上、自分の仕事を正当に評価してくれる人に着てもらいたいと思っているだろう。私達流通業者は彼らの作品をきものを着る人に紹介し、橋渡しするのが生業である。橋渡しの役を負っている以上、問屋や小売屋は作品に対する理解と知識を持ち合わせなくてはならない。ちょうど骨董屋さんが目利きをするように。創造と消費との狭間に立ち、消費者へはその作品がどのような価値があり、意味のある物なのかを説明し、作者には採算を度外視したような作品は消費者には受け入れられないということも話さなければならないこともあるかもしれない。
そこには作品の創造的価値と金銭的価値との調整とでも言うべき役割がある。
しかし、今日の業界はその役割を放棄しているようにも思える。問屋や小売屋、私も含めて全ての呉服流通業界の人達が作者の創造的価値を考える事もなく、金銭的価値ばかりを追っているのではないだろうか。
竹田さんはそのことを敏感に感じているのかもしれない。問屋と取引すれば、知らないところで作者が意図しない、とてつもない価格で販売されたり、大先生に祀り上げられ名前と作品が一人歩きしてしまうことがあるという事を。
私が竹田さんと知り合ったのはインターネットを通じてだった。竹田さんが私のホームページを見てメールを下さったのが始まりで、それ以後幾度かメールをやり取りしている。しかし、竹田さんと私の間には大きな壁があった。小売屋として織の訪問着をどのように扱い、消費者に何と説明したらよいか、という命題である。(『続続きもの春秋五、呉服屋は文化の創造者になりえるか』参照)
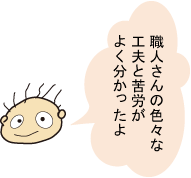
竹田さんは確固たる信念を持ってすくいの訪問着を織っていた。その作品が第一級の工芸品であることは論を待たない。実際、竹田さんは幾つもの工芸賞に入選している。 織の訪問着を消費者にどのように説明するかという前に、小売屋として竹田さんの創作する作品を消費者に紹介する義務があるように思えた。黙って作品を紹介し、消費者、きもの文化の担い手である日本人がそれをどのように評価しきもの文化を継承しようとするのか。それも小売屋の一つの役割ではないだろうか。
(文中、竹田さんの意向により、敬称を「さん」とさせていただきました。)
竹田さんの作品をご覧下さい。→| 竹田しのぶ作品集へ |

