全日本きもの研究会 きもの博物館
35. 村山大島
昭和30~40年代に呉服店の店頭を飾った反物があった。昭和30年代といえば、日本は戦後の終焉を宣言し高度経済成長期に入った頃である。戦争で灰塵に帰した日本経済が再生し、生活に余裕ができ、きものの需要も増え、業界が活況を呈していた頃である。
ゆかたは夏場店頭に山積みにしておけば1人2~3反買って行ったと言う。いくら呉服業界が活況であっても、高額な留袖や訪問着も飛ぶように売れたわけでない。今よりははるかに、「飛ぶように」という表現が当てはまるかも知れないけれども、高級呉服は当時でも普段着ではなく晴れのきものとして高価だった。
先に記した店頭を飾っていた反物とは、一つはウールであり、もう一つは村山大島である。村山大島と聞いて懐かしく思われる方も多いかも知れない。当時、村山大島のアンサンブルはウールと並んで呉服店の店頭を飾っていたのである。
村山大島は、高級呉服としては扱われずに普段着のきものだった。きもののTPOで言えば村山大島も本場大島紬も普段着に違いはないが、後者は高級呉服として扱われ、今でもきものを着る人にとっては高級品のレッテルが貼られている。
私が業界に足を踏み入れたのは昭和五十年代後半である。当時既に呉服の需要に陰りが見え、特に普段着としてのきものが激減し始めた時だった。村山大島を扱う問屋は少なく、私のいる問屋でも、もはや村山大島を扱っていなかった。それでも得意先の中ではまだ店頭にウールとともに村山大島を並べている小売店もあった。
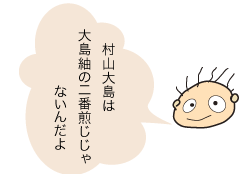
京阪神を担当していた私は大阪の下町の呉服店で並べられている村山大島を見ると何故か心が和んだ。ウールや村山大島など普段着のきものが店頭に並んでいると、きものもまだ捨てたものではないと感じたものだった。
村山大島が呉服店の店頭から姿を消したのは普段着のきものの需要が減ったからに他ならない。ウールや他の紬と同様に普段きものを着ている人が少なくなり、きものの需要はより高級なものに偏ってしまったからである。当時は、
「大島紬は高くて変えない。」
「大島紬を普段に着るのはもったいないので。」
といった人たちが村山大島を買い求めていた。大島紬の数分の一の価格の村山大島は当時普段着として十分な市民権を得ていたのである。
しかし、そのような言い方をすれば、『村山大島』という名称とあいまって、 「村山大島は大島紬の二番煎じ」あるいは、「安物の大島紬」と思われるかも知れない。確かに村山大島は大島紬を買えない人たちが着ていたのは否めない。しかし、村山大島は村山大島としての歴史と技術に裏打ちされ織られたものである。
村山大島は大島紬を模して創られたという側面は確かにある。「模して創られた」と聞けば、大島紬の模造品と思われるかも知れない。もっと口悪く言えば偽物と言われるかも知れない。現代の世の中、偽物がまかり通っている。高品質のコピー機やプリンターで造った偽札、偽造コイン、そしてフランスやイタリアの高級ブランド商品を真似て造った偽ブランド商品など大手を振るって流通している。あたかも騙されるのが悪いと言わんばかりに。そして、巷に多くの偽物がまかり通るのに反して真似ることは悪いことと誰しも思うかも知れない。しかし、古来日本では真似るというのはそれらとはまるで違った意味を持っていた。
もともと日本語の「学ぶ(まなぶ)」という言葉は「学ぶ(まねぶ)」(他のものに似せて言ったり行なったりすることを指す)から来ている。弟子が師匠の技を「まねる」ことが「まねぶ」であり、それは「習得する」「勉強する」の意となったのである。先進の技術を「まねる」ことは「学ぶ」ことであって、それは粗悪な偽ブランド商品を製造販売するのとは全く違った意味を持つのである。

染織の世界で「学ぶ」ことはよく行なわれてきた。「秋田八丈」は「黄八丈」を手本としたものであり、「米琉(米沢琉球)」は琉球絣を手本としている。加賀友禅は京友禅の技術を取り入れたもので、それぞれ手本の良さを取り入れながら地元の持味を出している。村山大島もその例に違わない。
村山大島は現在の東京都武蔵村山市、瑞穂町を中心に埼玉県飯能市、入間市あたりで1919年(大正8年)頃に生産が始まった。それ以前は当時の日本全国がそうであったように、地元の織物があった。江戸時代には所沢を中心とした村山絣、立川の砂川太織、蕨の双子織などが名声を誇り、それらを基盤として村山大島が生まれたのである。
村山絣は、文化年間(1804~1818年)に渡辺助右衛門の妻まさが十字模様の絣を考案、ついで天保年間(1830~1844年)に内野忠兵衛の妻きそが井桁模様の絣を織出したことに始まると言われている。この時期は丁度井上伝が久留米絣を考案した頃と期を一にしている。女性の創意工夫が日本の織物を支えてきたのである。
名声を得ていた村山絣が何故大正年間に村山大島に転身したのか、詳しくは分からないが私は次のように推察している。
村山大島の手本となる大島紬が商品として本土に出回るのは明治十年頃。泥染と精緻な絣が珍重され、全国にその名が知られるようになる。大島紬はもともと久米島紬から伝わったと言われているように紬糸を使った織物だった。それが大正に入り生糸を使うようになり、現在のような地薄の織物となったのである。
生糸を用いることにより軽くて丈夫な大島紬は全国の女性を魅了したのだろう。いつの時代もヒット商品に追随して商品開発が行なわれるもので、村山絣も大島紬に追随して紬糸を止め生糸を使い、大島紬と似た風合いの絣地を創ったのだろう。大島紬、村山大島共に他の絣と大きく違うのは紬糸を使わずに生糸を使っていることである。しかし、村山大島は伝統的な村山絣の持ち味を活かして絣を括りではなく板締めで行なっている。大島紬は絣柄を糸で締め上げる括りで行なうために莫大な手間がかかる。しかし、村山大島は板締めで行なうために大島紬程の手間はかからない。村山大島が安価にできる所以である。
当代のヒット商品である大島紬を参考にして、その名を借りたとは言え大島紬と村山大島はその生い立ちも製作方法も別物である。その名の故に村山大島が大島紬の二番煎じのように解されるのは、創意工夫を凝らして村山大島を世に出した先人の本意ではなかっただろうと思う。
村山大島が店頭から姿を消した訳はもう一つある。韓国大島の登場である。
昭和50年頃は今よりはまだきものの需要が多く、普段着も良く売れていた。手間暇のかかる大島紬は価格が高く、庶民には高値の花だった。その頃力をつけてきたアジアNIES諸国ときもの業界の利害が一致したのか、きものの海外生産が行なわれるようになってきた。縮緬などの白生地から始まり、安い労働力と手先の器用さを買って韓国や中国で帯地や織物が造られるようになっていた。
私が京都にいた50年代後半には中国の帯や白生地が相当数出回るようになっていた。そして、大島紬も韓国大島の名で出回っていた。単純な亀甲柄であれば労働力の安さに物を言わせて奄美や鹿児島産とほとんど変わらない物が三分の一程度の値段で取り引きされていた。
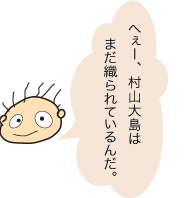
きものナショナリズムに固執する人の中には韓国や中国のきものに手を出そうとしない人がいる一方で、安価であればと結構売れていたように思う。村山大島とそう変わらない価格で手に入る韓国大島に、
「値段が同じであれば、村山大島よりも韓国大島の方が・・・。」
と相当数需要が流れてしまった。
普段着の減少と韓国大島の登場で村山大島は店頭から姿を消すこととなってしまった。
先日、問屋さんと話していた時のことである。
「村山大島は最近見かけませんが、今でも織っているのですかね。」
「ありますよ、産地は結構元気ですよ。」
応えは意外だった。私はここ20年程村山大島にお目にかかっていない。
「今度持ってきますよ。直ぐに取り寄せられますから。」
そして数週間後その問屋は村山大島を抱えてやってきた。久しぶりに見る村山大島は新鮮だった。昔はアンサンブルだけだったけれども、今は着尺(一反物)も造っているという。
「機屋さんはもう数件しか残っていませんが、皆一生懸命ですよ。」
きものだけではなく伝統的産業に共通して言えることだけれども、最後の最後まで伝統技術を残そうとする努力は並大抵ではない。斜陽になった産業にいち早く見切りをつけることは容易いが、最後まで技術を守ろうとするのは難しい。まして高価で鳴らした織物ではなく、普段着として扱われていた村山大島である。今まで織続けてきた機屋さんには敬意を表したいと思う。
村山大島をもう一度見ていただきたい。確かな伝統で裏打ちされた村山大島は昔見たそれとは全く違ったものに見えることと思う。

