全日本きもの研究会 きもの博物館
48. 黒留袖
黒留袖が女性のきものの第一礼装であることは、少々きものに興味のある人ならば知っている。皇室では黒留袖を着ないので色留袖が第一礼装との講釈もあるけれども、少なくとも庶民の間では黒留袖が第一礼装であることは衆目の一致するところである。
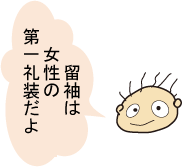
黒留袖を着る機会はどれだけあるだろうか。一番見掛けるのは結婚式である。新婦の隣に座る仲人、新郎新婦の母親、既婚の姉妹、親戚など。結婚式ではどこまで黒留袖を着るべきかという質問もよく頂戴する。新郎新婦の母親、既婚の姉妹は当然としても、祖母、叔母等どこまで黒留袖を着るべきかという質問である。
答えは、
「はっきりとした決まりはありません。」
というのが正解だろうと思う。しきたりは地方や家によっても違うし、親族席の黒留袖姿の女性は結婚式にはなくてはならない。誰が着るべきかを詮索するよりも、新郎新婦の門出を祝福する気持ちを優先すべきだと思う。

黒留袖が着物である以上、袷、単衣、薄物がある。しかし、黒留袖といえば袷しか見たことのない人も多いのではないだろうか。6月や9月であれば単衣の黒留袖を着なくてはならないし、7、8月であれば薄物の黒留袖を着なくてはならない。しかし、単衣や薄物の黒留袖は見かけない。
昔は結婚の季節は春か秋に限られていたからだろうか。それとも、余り着る機会のない黒留袖を何枚も用意できないので袷しかないのだろうか。実は単衣も絽の黒留袖もある。私もこの20年間に2枚だけ絽の留袖を扱った。黒留袖を着るのは結婚式ばかりとは限らない。謡曲を嗜む人は正式な舞台では黒留袖を着る。季節の舞台用に単衣や絽の黒留袖が必要なのである。
最近は真夏の結婚式も増えてきた。真冬、年末年始の結婚式もある。
真夏は結婚式場の料金が安かったり、休みを取れない人は年末年始の休暇を利用して新婚旅行をする、という事情もあるけれども、やむにやまれず式を挙げるという事情もあるらしい。
呉服屋にとっては年中結婚式があれば単衣や薄物の需要が増えて良さそうだけれども、単衣や薄物の留袖の注文は一向に入らない。やはり、
「それ程着る機会のない黒留袖をわざわざ単衣や薄物まで作らなくても。」
ということらしい。
しかし、いかに結婚式場の冷房が効いて涼しかろうと、真夏の結婚式に袷の黒留袖はどうもいただけない。せめて単衣の黒留袖を着ていただきたいと思うのである。それでも、
「単衣の黒留袖まで・・・。」
とは誰しも思う。そこで次のようなのはどうだろうか。
わざわざ新調する必要はない。古くなった留袖を単衣に仕立て直すのである。母や祖母に譲ってもらった留袖とか、少々派手になった留袖があるはずである。それを仕立て替えれば単衣の留袖として十分に着られる。本人にとっては満足できない柄かもしれないが、許せる範囲ならばきものの季節感を守っていただきたいのである。
さて、話は変わるけれども、『留袖』という言葉はどういうきものを意味しているのだろう。きものの名称は時と共に意味が変り、原初の意味とは掛け離れているものが多い。この『留袖』もその例に違わない。黒留袖の事を『江戸褄』と呼ぶ人もいる。
物の本には、黒留袖と江戸褄は同義としているものもある。この江戸褄という言葉も含めて、その語源を探ってみたい。 『留袖』の元々の意味は、文字通り袖が留めてあるきものである。留袖の対極にある袖を留めていないものとは振袖である。その昔、若い女性は袖を縫い塞がない振りのあるきもの、すなわち振袖を着ていた。そして、結婚すると袖を縫い塞いで留袖としたのである。「袖」というのは日本人にとって特別な意味を持つ。 「袖の下」「袖にする」「袖を引く」「袖を濡らす」「袖を絞る」など、袖というのは日本人の生活に深く関わっているのである。
「あかねさす紫野行き、標野行き、野守は見ずや君が袖振る」
万葉の時代には、若い女性が男性を誘惑する時には袖を振ったらしい。そして、結婚した後は他の男性に袖を振られてはたまらない、ということだろうか。袖を留めた留袖を着たのである。昔は袖を完全に閉じて身八つ口も無かったけれども、江戸時代に入り帯の幅が広くなってくると身八つ口が設けられるようになって現在のきものの形になった。
つまり、留袖という原初の意味は、その精神が残っていると言っても良いかもしれない。形式上は完全に袖を留めた留袖ではなくなっても精神的には袖を留めるべき人が着るきものなのである。
さて、留袖の事を江戸褄と呼ぶのは何故だろう。私もいろいろと調べてみたが、次の通りらしい。
江戸褄というのは柄の配置の形式を表わす言葉だった。「江戸褄」と同様に柄の配置を表わす言葉として「島原褄」というのがあった。どちらも昔の引き摺りの形式で、今の留袖のように前身頃を合わせて帯を締めるのではなく、長いガウンのように引っ掛けて裾を引き摺るきものの形式である。殿中のお姫様、大奥を想像していただければ良い。
現代の絵羽のきものは、前を合わせるために上前には柄を多く配し、下前は隠れてしまう為に柄が少ないのが普通である。黒留袖を衣桁に掛けてみれば向って左の方が柄が大きく、右の方へ行くにしたがって柄が少なくなっている。
しかし、引き摺りの場合、裾を引いて見せる為に柄は左右対称に描かれる。上前も下前もないのである。現在のきものの柄配置とはまるで違っている。
島原褄とは京都の遊郭島原が語源である。島原の遊女は衣装を華やかに見せる必要があったのだろう。柄は剣先あたりまで高く柄が配されていた。左右対称に描かれたのでV字型に柄が大きく配され、おくみの柄が衿までとどいている物もある。
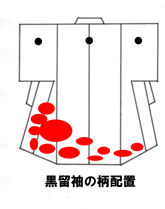
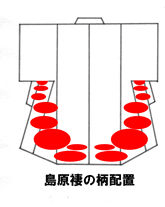
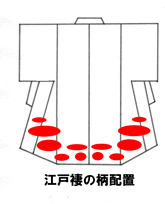
それに対して江戸褄と呼ばれる引き摺りは柄が低く裾模様の様に見える。江戸褄の「江戸」とは「武家」の換言だろうか。質素を旨とする武家の心が反映されているように思える。
昔の(昭和初期)の黒留袖を見ると、柄は今のような華やかなものではなく、裾に低く柄を配したものが多い。その柄の配し方が江戸褄の形式であるという意味で黒留袖を江戸褄と呼び習わしたのだろう。
留袖、江戸褄、どちらも原初の意味とは換わっているだけに、どちらが正しいとか、どちらで呼ぶべきかという議論は成り立たないように思う。 さて、話は戻るけれども、結婚式で着られる留袖姿も最近は益々減ってきている。
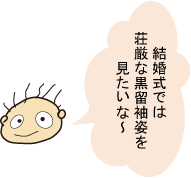
結婚式の形式も変わり、仲人を立てない結婚式も多い。又、友人を集めて行うレストラン披露宴など、「御親族」という肩書きそのものが消えうせてきている。山形のような地方では、まだまだ仲人、親族の黒留袖姿は見られるけれども、東京では仲人や新郎新婦の母親でさえ黒留袖を着ないケースも多いらしい。式は簡略化し、晴と假の区別がなくなってきている。しかし、今の世の中に一番足りない物は晴と假の区別であり生活のメリハリではないかと思う。
昔、正月といえば荘厳に迎えたような気がするけれども、最近は大型店は平日の如く店を開き、ただの一休日となってしまった感がある。雛祭りや五月節句、お盆、月見などの特別であった日も何の感慨も無く過ごしてしまっているこの頃である。結婚式も人生の大切な節目として迎えてきたけれども、只のパーティになってしまうのは寂しい気がする。
日本女性の第一礼装、黒留袖を後世に伝えてもらいたいと思うのである。
関連記事
「続きもの春秋 13. 紬の留袖」
「きもの春秋 18. きものの格式」
「きもの博物館 18. 石持」
「きもの講座 2. きものの格について」

