全日本きもの研究会 きもの博物館
11. 下駄
きものを着る時には、きものがあれば良いわけではない。下着となる襦袢も必要だし、帯も必要である。帯締や帯揚といった、いわゆる和装小物もかかせない。きものを買いにくる人から次のような声がよく聞かれる。
「きものを着ようと思っても、裏や仕立て代がかかり、襦袢や帯、その他あれやこれやと必要になるのでとても高くついてしまうんですよね。」
きものが高いか安いかについては、「きもの春秋」にて述べているので、ここでは繰り返さないけれども、きものを着る場合にはきもの一枚で事足りないのは当然である。これはきものに限らず洋服でも何でも同じことで、きものの欠点というにはあたらない。
男性の洋服でもスーツを着るにはワイシャツがいり、ネクタイがいる。ベルトも靴下も靴もいる。それぞれ吟味すれば、そこそこの値段になってしまうのは衆目の一致するところであろう。しかし、きものの事となると知識が不足しているせいか、
「そんなものもいるんですか!」
という目で見られてしまうのである。

きもの、帯、襦袢までは誰でも吟味しても、その他の小物まで吟味すると言うのはなかなか難しいようである。
小物の中でも帯締や帯揚は直接目に見えるので吟味するけれども外からは見えない伊達締めなどは余り消費者の目にはと留まらない。
かく言う私も、きものや帯の仕入れには十分に時間を費やすけれども、小物にはそれほど気を使っているとは言えなかったかも知れない。そんな事もあって、今回は浅草、花川戸の下駄屋を訪ねてみた。
下駄は和装小物の一つである。草履と並んで外を歩く時には無くてはならない履物である。しかし、下駄と言うとどうも軽く見られているようである。
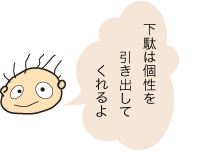
「下駄ばきで・・・」という言葉がある。これは、「普段着で・・・」という言葉よりもまだカジュアルな、「相手に失礼な・・・」という響きさえ感じられる。
下駄は決して下賤なものではないのだけれども、「ゲタ」という言葉の響きは、その濁音もあいまって上品には聞こえない。
最近は洋風文化の波にのまれ、絨毯を敷いたホテルや結婚式場では、「下駄履きお断り」と言う看板が下駄の地位を落としめているのではないかとも思う。ひいては石畳を歩けば、カランコロンと音がする下駄の音が、音をたてることを極端に嫌う西洋文化に嫌悪感を抱かせたのかも知れない。下駄の音と蕎麦をすする音は、私にはとても日本的な快い響きに聞こえるのだけれども。

さて、私の店でも昔から下駄を扱っている。扱っている、と言っても、和装小物の問屋が持ち込む物を何の知識もなく並べているだけだった。
しかし、花川戸の下駄屋を訪ねると、私の下駄に対する考えは一変してしまった。一変した、というのは下駄屋さんには甚だ失礼な話で、ただ私の下駄の知識が足りなかったというだけなのである。
考えてみれば、自分の属する呉服業界と同じように、下駄の業界もあるのである。私が業界に入って20年たってもまだ呉服については分からないことだらけである。他の業界の事が分からないのは当然である。
花川戸、浅草、言問橋から吾妻橋の間には戦前200軒を越える下駄屋があったという。そして今はわずかに五軒。今では靴屋さんが多く店を開いて、履物の町の看板は変わってはいないけれども昔を知る者にとってはまるで様変わりだという。当時の日本の人口は8000万人。ほとんどの人が下駄を履き、旦那衆は正月には使用人に下駄を与えたという。
「下駄は消耗品だから下駄屋になれば食いはぐれないと思って下駄屋になったんですよ。」
とは、下駄屋の主人の言である。
下駄を仕入れる時に、私が最初に戸惑ったのは下駄の鼻緒である。
下駄には鼻緒がつきものである。私の店で仕入れた下駄には皆鼻緒が初めから付いている。しかし、下駄の問屋では下駄と鼻緒はいわば別売りである。下駄をいくつか選んだところ、
「鼻緒はどれを付けましょう。」
と、聞かれた。さて、その鼻緒はと言えば壁面一面にずらりと並べてある。別珍の無地の鼻緒から、ヘビやトカゲ、オーストリッチの鼻緒。印傳や友禅の鼻緒。そして最近ではデニムや下駄を履き慣れない人の為のハイテク鼻緒と言えるような鼻緒まで所狭しと並んでいる。

下駄には下駄の値段があり、鼻緒には鼻緒の値段がある。組み合わせて仕入れ値がいくら、となるわけだけれども慣れない私にはピンとこない。そして、値段もさることながら下駄の鼻緒にも仕来りがあるはずである。留袖に紬の帯をするようないい加減な合わせ型はできないのと同じように下駄と鼻緒にも相性があるはずである。
一足二足選ぶのであれば、下駄屋の話を聞きながら選ぶこともできるけれども、数がおおいので時間が無い事もあり、その場は、
「おまかせしますから。」
と言って来るほかなかった。やはり、下駄の世界は下駄の世界である。普段何気なく履いている下駄だけれども、話を聞けば奥の深いものがある。下駄に限らず全てがそうなのだろうけれども。
下駄の材質は一般に桐が良いと言われている。柾目であることは言うまでもない。しかし、そこで見せてくれた下駄は杉材だった。「神代杉」(じんだいすぎ)と言って、飛騨地方の極一部の産地でしか採れないものである。よくある杉の下駄と比べて見せてくれた。軽くて目のしまった柾目の下駄だった。桐のように白くはなく飴色の渋い下駄である。
「これはもう余り採れなくなったのでうちしか扱っていないんですよ。」
下駄屋の主人が自慢げに話してくれた。上品とは言いがたいけれども、木の年輪や下駄の歴史を感じさせてくれるような下駄である。
きものの好きな人が浴衣をきる時にはぴったりだと思い、いくつか注文したが、今度はどの形の下駄にするのかと言われる。下駄の形など余り意識したことのない人がほと んどだと思う。幅の広い下駄、狭い下駄。LサイズかMサイズか、位しか私の頭にはなかった。神代杉の女物の下駄は、三種類作られていた。「芳町」「小町」「右近」の三種類である。
「芳町」は二枚歯のいわゆる下駄である。「小町」は前の歯が下駄の先から斜めに切ってあり、「のめり型」とも言う。「右近」は歯のない草履型の下駄である。実は下駄の形にはまだまだ種類がある。私の知識不足や紙面の関係もあって全て書き尽くす事はできないが、いくつか紹介すれば、「デカンショ」とも言われる朴の歯を埋め込んだ朴歯下駄、昔花魁(おいらん)が履いたような三つ歯の下駄。

(本当の花魁が履く高さが三十センチもある「おいらん下駄」も年に数足売れるそうである。)男の下駄で「小町」と同じように先が傾斜した下駄を「千両」という。
特殊な下駄では力士が履く大型の下駄。(もちろん別注である。)役者が履く六角形の下駄など。
役者と言えば、役者の履く下駄のほとんどがこの下駄屋で作られている。最近はなくなったけれども、昔の役者(現役役者の先代か先々代まで)は自分の履く下駄に事細かに注文をつけていたという。下駄の大きさはもちろんのこと、歯の幅や位置。鼻緒の穴の位置などひとりひとりが最も履きやすい寸法を指定していたそうである。
下駄の別注と言えば、現代のスポーツ選手が自分の足に合わせて靴を作るのを彷彿とさせる。 「最近の役者さんはそういう事はなくなりましたがね。」 と、ちょっと寂しそうな表情で下駄屋の主人が言ったのが印象的だった。
鼻緒の位置と言えば、関東と関西で鼻緒の付け方が違うことは良く知られている。関東では前鼻緒、すなわち後ろの歯の前に鼻緒の穴を開けて止める。関西では歯の後ろに穴を開ける。私も以前から疑問を持っていた。関西と関東では下駄の歯の間隔が違うのだろうかと。
そのことを聞くと、見本を取り出して話してくれた。
「関東式、関西式という事はありません。うちでもこのように後ろ鼻緒の下駄も作っています。ただやはり関東では前鼻緒が圧倒的に多いですがね。」
「歯の間隔が違うんですか。」
「いいや、歯の間隔は同じですよ。後ろ鼻緒の方は鼻緒が後ろまで来るので足がしっかりと入るんですよ。」
「それじゃあ、やはり江戸っ子は気が短いんで下駄を脱ぎやすいように前鼻緒にしているんでしょうかね。」
「それはあると思います。」
関東と関西の下駄の鼻緒の違いは関西のなれ寿司と江戸前寿司との関係にも似ているようである。
下駄の名前はそれぞれ奥ゆかしい名が付けられている。下駄の名前にはゆかりが有るのかと思い聞いてみた。
「『芳町』や『小町』という名はどこから来ているのですか。」
『芳町』は芳町芸者を『小町』は小野小町を連想させる。
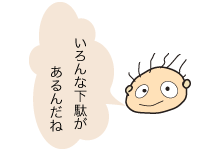
しかし、下駄屋の主人は困った顔をしていた。
「そういう質問は良く受けるのですが、はっきりとした答えはありませんよ。昔、誰かが商品を区別するために粋な名前を付けたのでしょう。」
他にも下駄には、胡麻竹を張った下駄、塗り下駄、鎌倉彫を施したものなど書きつくせぬ程の種類がある。きものや帯の種類を覚え、その組み合わせを覚えるのと同じ位、下駄の世界も実に奥深いのである。少ない紙面で紹介しようと言うのがおこがましく思えてくる。もしも、私が下駄屋であれば「きもの春秋」ならぬ「下駄春秋」を著さなくてはならない。
きものを着るための小道具の一つである下駄を吟味してみるのも面白い。粋なきものの着方ができそうである。

