全日本きもの研究会 きもの博物館
18. 石持
きものには洋服同様に様々なアイテムがあるけれども、弔事に着る着物を何と呼ぶだろうか。
そのものズバリ『喪服』である。『喪服』は黒の無地で五つの紋を付ける。紋を付けるので『黒紋付』とも呼ばれる。又、『石持』と呼ぶこともある。『石持』は「こくもち」と呼び、あらかじめ紋を付ける所を白く抜いたものを指し、必ずしも『喪服』を指す訳ではない。黒留袖や色留袖でもあらかじめ紋の部分を白く抜いたものは『石持』である。しかし、黒留袖や色留袖を『石持』と呼ぶことはない。この辺りが着物用語が曖昧であると言われる所以である。
『紋付』と言えば広義に紋の入った着物全てを指す。黒留袖、色留袖、色無地、江戸小紋に紋の入ったもの、男の黒紋付、色紋付など。『喪服』は紋付の一つに過ぎず、『紋付』の十分条件ではあるけれども必要条件ではない。
『石持』という言葉は業界の専門用語で、初めて業界に入った新入社員は「いしもち」と呼んで笑われたり、「黒持」と書いて叱られたりするのである。(私がそうだった。)
しかし、石持の名前の由来をたどれば、「石持」はもともと「黒餅」だった。白地に黒の餅を型どった(ただの黒い丸)紋が黒餅紋。黒地に白の餅を型どった(ただの白の丸)紋を白餅紋と呼んでいた。それが白黒の別無くどちらも「黒餅」と呼ぶようになった。「石持」という字が当てられたのは、武士にとって一定の石高をもらう知行取りに通じ、縁起が良いとされたためだと言う。日本人は何とダジャレの好きな国民なのだろうか。


洋服の世界ではどうだろう。黒の装いはブラックフォーマルと呼ばれる。黒の礼装、礼服などと呼ばれることも有るけれども、それらは英語と日本語の裏返しにしか過ぎない。
それでは何故『喪服』を『紋付』『石持』と言い換えて呼ぶのだろうか。私が問屋にいた時には、伝票に『喪服』と記載することはなく、『黒紋付』あるいは『石持』と書くのが普通だった。今でも私は伝票に記載する際に『喪服』と書くのに抵抗感を覚える。
『喪服』と言う言葉は忌み言葉である。誰しも余り使いたがらない。忌み言葉を避けられれば避けたいというのが日本人の心情である。
「アシ」と呼ばれる植物が有る。パスカルが「人間は考えるアシである。」と言った、あの水辺に生える「葦」である。しかし、「アシ」は「悪し」につながるというので、いつしか「アシ」(悪し)は「ヨシ」(良し)となってしまった。外国ではこういう文化があるのかどうか知らないけれども、少なくとも日本文化の深層ではないだろうか。やはり日本人はダジャレが好きである。
『喪服』と書かずに『黒紋付』『石持』と書くのはその辺の事情にあるのではないだろうか。非常に曖昧な言い方ではあるけれども、『喪服』を『紋付』『石持』と言い換えても少しの不便も感じた事はなかった。女性の喪服と男性の黒紋付を取り違えることはなかったし、「石持を持ってこい」と言われて、黒留袖や石持の色留袖を持っていったという話は聞いたことがない。日本人は話の前後の筋道から巧みに使う言葉の意味を変化させている。
『喪服』という言葉が忌み言葉であるように「喪服をつくる」のは振袖や訪問着を作るのとは違って、積極的な意味を持たない。誰しも必ず必要な喪服なのだけれども、縁起をかついで作る時期を選ぶ人が多い。中には必要にせまられてつくる人もいる。「必要にせまられて」というのは良いことではないけれども、年に数回そういった注文を頂戴する。
着物を一着仕立てるのに通常二~五日ぐらいかかる。専門に仕立てをやっている人と主婦の合間にやっている人では違うけれども一週間もかからない。しかし、注文を受けても順番待ちで、お客様には1月~1月半の時間を頂戴している。
しかし、必要に迫られて喪服を作る場合、そんなに待ってはいられない。時には「明日まで」とか「明後日まで」と言われる事も有る。できるだけお客様の希望には応えたいと思うけれども、喪服は紋付である。紋を入れなければならず、すぐに仕立てと云うわけにはいかない。石持の反物を紋屋に持ち込み、至急紋を入れてくれるように頼み込み一日。そして、仕立屋に走り、拝み倒して一日半。お客様にお渡しするのは三日が限度である。喪服については、
「必要に迫られたら、余裕を持って喪服を作ってください。」
とも言いにくい。まして、必要に迫られなければ喪服を作るのは気がひける。そこで縁起をかついで喪服を作る時期と場所を選んだりするのである。
お盆や彼岸といった仏事に作る。あるいは逆に正月に作る、と云う話も聞いたことが有る。時期を選ぶのではなく揃え方を工夫して喪服から帯締め帯揚げ、草履バックまでの喪装を完全には揃えずに(例えば草履は揃えない)などの工夫がされる事もあるようだけれども、人により地方により様々なようだ。どちらにしても、自分で納得できればよいのであろう。
さて、柄のない無地の黒紋付というのは何のおしゃれ気もない着物と思われるかも知れない。同じ黒の紋付である黒留袖は裾の模様でおしゃれを競っている。京友禅や加賀友禅の留袖は作家が心を込めて描いた個性である。数万円で買える黒留袖から、数百万円もする黒留袖まで、その種類は千差万別である。それに比べて黒の無地はどれをとっても同じ黒と思われるかも知れない。しかし、黒という色は非常に難しい色なのである。
小学校の図工の時間を思い出して欲しい。色の分類という勉強をしたことが有ると思う。大きく分ければ黒と白(灰色も含む)が仲間でそれ以外の色とは区別される。白と黒は無彩色と呼ばれ、その他は有彩色である。プリズムで分光された七色(本当は七色ではなく連続的な無限の色数である。)を全て吸収するのが黒色、全てを反射するのが白色である。全ての色を吸収するのが黒なのだから、黒と云う色は一つしか有りえない。しかし、そのたった一つの黒を作るのがむずかしいのである。
色は三原色(赤、緑、青)でできており三つの色の染料を等分に混ぜると黒ができるはずである。しかし、絵の具でいくら試してみても黒を作ることはできない。どす黒く汚い色にはなるけれども、真っ黒と云えるものはできない。
多色刷り(カラー)印刷物を発注したことのある人であれば良く分かる事である。カラー印刷は三つの色を重ね刷りして色を出す。しかし、前述の通り三色のインクを等分に重ねても(真)黒にはならない。そこで三色の他に黒のインクでもう一度重ねて四色刷りとするのである。予算をけちって三色刷りでカラー印刷を頼めば間の抜けたカラーになってしまう。
着物の染色も同じで、真っ黒という色を出すのに染屋さんは工夫に工夫をこらしている。
黒紋付(喪服)の反物には『紅下染』とか『藍下甲州黒』というような表示が有るのに気がついた人も多いと思う。他にもいろいろな表示が有るけれども、黒という色は一度で染めることができないので、紅色に下染をしたり。藍色に下染をして黒の色を出していく。
下地に使った色によって「少々赤みを帯びた黒」とか「青みがかった黒」ができる。それぞれの反物一つ一つを見れば真っ黒に見えるのだけれども、並べて見ればその色の違いは歴然である。真っ黒と思って見ていた黒が他の黒と比べてみると茶色に見えて来ることもある。それほど黒という色は微妙で染めるのが難しい色なのである。
また、同じ染め方で染められた黒でも生地によって微妙に変化してしまう。黒に限らず、色無地でも別染めを頼まれてお客様の指定の色に染めることが有る。
色見本帖を開き、お客様が自分の好きな色を選び染めるのだけれども、できてみると色が微妙に違ってみえることが有る。染屋が間違った訳でも下手な訳でもなく、色は指定通りに染めているのだけれども、生地の光沢が違っていたり、シボが大きかったりすると色の印象が違ったものになるのである。
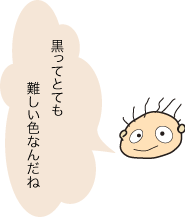
昔は喪服といえば羽二重生地を使っていた。現在還暦を迎えようとする人達が嫁いできて時に作った喪服はほとんどが羽二重の喪服である。しかし、最近(10~20年位前から)は縮緬の喪服が主流となっている。いまだに、「紋付(喪服)は羽二重」とかたくなに娘さんの喪服を羽二重で注文する客もいるけれども、99パーセントは縮緬である。
どちらが良いとは云えないし、それぞれの個性で着るのが着物なのでしっかりとした生地ならばどちらでも構わないと私は思っている。しかし、羽二重は光沢があるので縮緬と比べるとどうしても白っぽく見えてしまう。
生地と染め方により黒は千変万化するのである。一時に(弔時に)皆揃って着るだけに、並べば黒の違いが際立ってくる。柄のない黒一色の喪服は他に誤魔化しようの無い着物である。
柄のない喪服は年齢を選ばない一生物である。喪服は生地、染ともに吟味して良いものを作ったらどうだろうか、と言えば呉服屋の売り口上と取られるだろうか。
関連記事
「きもの春秋 18. きものの格式」
「きもの博物館 48. 黒留袖」
「きもの春秋終論 Ⅵ-37.またまた呉服業界の危機(羽二重がなくなる)」

