全日本きもの研究会 きもの博物館
8. 長板小紋中形本藍染(野口汎先生の事)
長板小紋中形本藍染という聞き慣れない染め物がある。名前は聞き慣れないけれども、見れば綿の藍染めである。その中型長板染めを染める職人はほとんどいなくなってしまった。中でも伊勢型の細かい柄を染められるのは現在野口汎氏ただ一人である。
私が野口先生と初めてお会いしたのは、新作浴衣の発表会だった。ファッションの世界は皆そうだけれども、夏物の浴衣の発表会は真冬の一月に行なわれる。正月気分が抜け切れぬ一月初旬に毎年東京で行なわれている。発表会では様々な浴衣に加えて、手拭や暖簾、巾着などが展示されている。私のような小売屋が新作に受注を付け、その数を基に、夏までに染めるのである。
手拭いのコーナーで、私は近くにいた問屋の人らしい人に幾つか質問した。しかし、傍らに立っていた「おじさん」の答えは要を得なかった。
「私は・・・ちょっと・・・。」
近くにいた若い人がやってきて手拭について説明してくれた。そして、隣に展示してあった長板染について質問すると、その「おじさん」は、人が変わったように事細かに説明してくれた
「こちらは、長板染めの野口先生です。」
問屋の若い人が私に言った。そうとは知らずに私は失礼な事を言ったものである。
一通り長板染めについて説明してくれた先生に私は、
「今度、一度先生の工房を見学させて戴きたいのですが。」
と言うと、
「ああ、いいですよ。」
と言って名刺をくれた。私はその時の印象が忘れられない。差し出された名刺を持つ先生の指先の爪の間には藍がこびりついている、というよりも藍が刺さっているのである。そして、その名刺の縁は薄ぼんやりと藍色に染まっている。その時、私は先生の手に職人気質を感じていた。

その一月後、私は先生の工房を訪ねた。
先生の工房、「野口染工場」は八王子にあった。八王子と言えば、東京近郊の町である。昔から織物の町として成り立ってきた八王子も、今では東京のベットタウンとしての印象が強くなってしまった。JR中央線で新宿を離れても家並みが途切れることはない。三十年程前までは、三鷹を過ぎれば、まだ田圃が残っていたけれども、今では見渡す限り家並みが続いている。

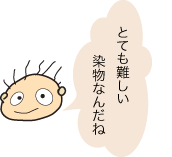
それでも立川を過ぎれば遠くに武蔵野の面影を残す林が家並みの間から見え隠れする。多摩川の鉄橋を渡り、日野市の辺りからは林も遠くに見られるようになるけれども、どこからが八王子市なのかが分からないまま、八王子駅についてしまう。
JR八王子駅よりバスに乗った。八王子の織物工業は時代の波に流され、ほとんどが機を止めてしまっているが、『織物組合』という停留所が往時の八王子を感じさせてくれた。約十五分、野口染工場に着く。バスを降りると、遠くの山際までマンションや団地が続いているのが見える。 『萬染物店』の古い看板を見つけ、門をくぐった。
「こんにちは、山形の結城屋です。」
ミシン掛けの仕事をしていた奥さんが出てきた。
「お待ちしてました。その土間を真っ直ぐに行って、向こうの建物で仕事をしていますので。」

藍瓶の並んだ土間を通りすぎ、少し離れた納屋のような建物の中をのぞき込んだ。先生は、板に張られた白生地に型を使って糊を入れている最中だった。私は戸を開けるのをためらった。先生が一枚分の型の糊を入れ終え、へらを上げたのを見て戸を開けて言った。
「山形の結城屋です。遅くなりました。」
少し緊張して言った私に先生は笑顔で、
「ああ、さっきまで向こうで待っていたのですが、遅いので仕事をしていました。」
そう言って、型を洗って、又へらで糊を入れ始めた。
先生は仕事をしながら長板染について説明してくれた。
長板染は、約六メートル(半反)の板に白生地を張り付け、型で糊を入れていく。もともとは、浴衣でも何でもそうやって染めていたそうだけれども、注染やプリントなど、染め方が多様になってきたために、長板という名前が用いられるようになったという。
型で糊を入れるごとに型を洗い、型を動かして糊を入れていく。型の継ぎ目が出ないようにするのが職人技である。無造作に型を動かしているようだけれども、継ぎ目はほとんど分からない程正確である。初めの型置きがわずかでも斜めに入ってしまえば、六メートル先では型が白生地からはみ出てしまう。
型染めに使われる糊には米糠が混ぜてあり、赤い染料が加えられている。糊を置いた白生地には型通りに赤い模様がついている。
「どうして糊に赤い染料が加えられるのですか。」
「白い糊だと型を継ぐ時に良く見えないんですよ。それと、裏返した時に、透けて見えないと、裏に糊を置くことができないんですよ。」
野口先生の長板染は両面染である。糊入れが終わると長板を天日で乾かし、今度は裏返しにして裏側にも同じ型(左右逆になるので型を裏返して使う)で糊を入れる。
「どうして両面に柄を入れるのですか。」
プリントであれば両面に型を入れるのは容易だけれども、両面の型をぴったりと合わせるのは至難の技である。それ程手間をかけてまで、という気持ちで質問した。
「両面に柄があれば、裾が返った時に柄が見えるでしょう。それに両面に柄を付ければ白い所はより白く残るんですよ。」
先生の言うことは当たり前と言えば当たり前であった。それだけに、
「そこまで手間を掛けて」
という気持ちが益々強くなっていた。
きものの裾は二尺も柄があれば事足りる。しかし、長板染めではその為に手間暇かけて裏側全部染めているのである。なんと日本のきものは贅沢なのだろう。
型で糊を入れる工程を見せてくれた先生は、
「型はこれくらいでいいかね。」
と言って、今糊を入れた板を外に出して天日に干した。
「糊が乾いたらここで豆汁(ごじる)を刷り込むんだよ。」
作業場の外には畑のような広場があり、そこで藍が良く定着するように豆汁を刷り込み、藍染めの工程に廻される。
母屋にある藍瓶の所に戻り、今度は藍染めの説明をしてくれた。土間には十数個の藍瓶が並んでいた。先生は用意していたガーゼのハンカチを伸子針で留めて藍瓶の蓋を開けた。
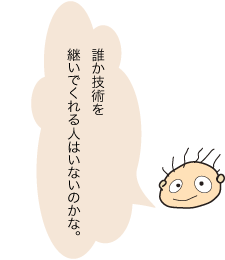
「こうやって静かに浸すんだ。」
静かにハンカチを藍瓶に沈める。しばらくしてから静かに瓶から引き上げた。引き上げられたハンカチはおよそ私が思っていた色とは違っていた。
「藍というよりは黄色ですね。」
「ええ、空気に触れた部分だけが藍色になるんですよ。」
「瓶覗(かめのぞき)とはこんな色の事ですか。」
私は知っている知識を搾り出して聞いたつもりだった。『瓶覗』とは藍瓶に一回漬けただけの薄い色という意味で、薄い藍色、水色の事を言う。
「まあ、それは言葉の上の事だから・・・。」
実際に藍染めをする者にとって『瓶覗』とはぴんとこないのかもしれない。
先生は太い棒で深さ一メートルもある藍瓶をかき混ぜ始めた。
「藍色は表面だけで、空気にふれていない中はこんな色なんですよ。」

先生がゆっくりとかき混ぜると、瓶の底から鈍い黄色の液体が沸き上がり、表面の藍色の液体と一緒になって二色の渦となった。泡が藍の花のように渦の中心に集まり、エキセントリックに回転している。先生としばし言葉を交わし、ふと先程の藍瓶に漬けたハンカチを見ると、ハンカチは真っ青に変色していた。
「まだまだ青くなりますよ。」
そう言う先生の言葉につられてそのハンカチを見ていると、みるみるうちに(という表現が適切か分からないけれども私にはそう感じられた)青さを増していく。頃合を見計らって、
「一反を漬けるときにはこすれて糊が落ちないように静かにゆっくりと漬けるんだ。」
と言いながら、今度は別の藍瓶にハンカチを漬けた。
十数個の藍瓶には、それぞれに個性があると言う。先生はそれらの藍瓶の個性を知り、我が子の機嫌を伺うように使う瓶を決めていく。
現代の科学を駆使した工場であれば、藍瓶の温度は、PHは、濃度は、比重は、など複雑な数字が出てくるのだろうけれども、先生の感はそれらを全て越えている。それらの藍瓶の中には七十年以上も前から使われているものもある。先生が子供の頃から供に育ってきた藍瓶である。初めてお会いした時に見た指先の爪に刺さった藍を思いだし、「先生は藍と寝泊まりしている」と思えた。
二度目の瓶からハンカチを取り出し、空気に晒し、藍色になったところで、それを桶に張られた水に浸した。柄を入れた糊を落としながら、薄く色の付いた水を指して、
「藍は染料じゃないから、一度落ちた藍は糊を置いた白いところを染めることはないんだよ。」
そう言ってハンカチを水から引き上げ、伸ばしながら天日に晒して干した。
先生の手仕事は糊を作ることから始まり、長板に生地を張り、型に糊を入れる。そして、藍瓶に浸け染め上げるまで全て一人でするのである。その手間と技術は大変なものである。
『手間を考えれば安いものですよ。』という呉服屋の売口上がある。『高いですね。』と客に言われた時の隠し玉である。それは嘘ではないのだろうけれども、自分も含め呉服を商う者のほとんどは人から聞きかじった受け売りにしか過ぎなかったのではないかと思えてきた。
このような職人技を目の当りにすれば、誰でもその技術が失われるのを惜しむだろう。テレビのドキュメンタリーででも放送されれば、きものにまったく関わりの無い人でも、「誰か後継者はいないのかな」と思うに違いない。
「先生、跡継ぎは・・・。」
月並みの質問とは思ったけれども聞いてみた。
「ああ、息子はいるにはいるんだが、どうするか迷っている所だよ。」
先生の答えは以外に淡泊だった。
伝統文化や職人技が消えていく。誰か後を継いでくれる人がいればいいのに、というのは回りの人間が思う感傷のようである。当事者である先生の言葉を聞けば、私は何も言えなくなってしまう。
「人に会うのが不得意な人、人と話をせずにもくもくと仕事をしたい人にはぴったりの仕事なんだけれどね。時にはあこがれてそんな仕事をしたいと言ってくる若者もいるんですよ。しかし、これからこんな仕事を始めようと思ったら、こんな設備を造るのも大変だし(藍瓶を指しながら)、四十歳位になって転職しようとしても、今時可哀想だしね。」
長板染の技術が伝承されないとしたら、一番寂しいのは野口先生自身だろうと思う。しかし、先生の言葉には、そういった感傷は感じられなかった。自分の生業としての仕事、自分が食べていく為の仕事という気持ちが感じられ、私の方が寂しい思いにさせられてしまった。
先生は野口染工場の六代目である。三代目までは京橋に店を構え、七十年前に先々代である四代目の時に八王子に移ってきたという。昔は染め職人も沢山いただろうし、それ程珍しい技でもなかったかもしれない。しかし、需要の減少と最新技術の発達で、染色の技術は手仕事から機械に移ってしまい、気がついてみれば昔からの仕事をしているのは自分しかいなくなっていた、というのが先生の思いではないだろうか。
一通り工程を見せてくれた後、お茶を飲みながら、先生はきさくに話をしてくれた。私もつられて先生に私の持論を話した。
「最近は完璧な物にお目にかかるようになって・・・。」
そこまで言うと、先生は私の意を察して、
「そうだよ、そうなんだよ。」
科学技術の発達で、身の回りには完璧な物が目に付く。プリントで染められた染物や八百屋の店先に並ぶ色も形もそろったキュウリやトマト。少しでも曲がったり色が悪かったりすれば、味はどうあれ商品価値がないかのように扱われている。本当の染めの良さや味の良さはないがしろにされている。(きもの春秋.15「手造りと難物の境」参照)いくら高度な職人技でも、コンピューターの精度にはかなわない。しかし、正確無比に造られた物には手造りの良さは感じられないのである。
「男物を染めてくれと言われて、縞柄を染めたことも有ったんだけどね、型の継ぎ目にはどうしてもいくらか線が入ってしまう。それが手造りの味なんだけれど、その良さを受けとめてくれる人が少なくなって、今は縞柄は染めないんだよ。」
先生の言葉には、時代の波に逆らうことなく素直に受けとめ、自分ができる仕事を精一杯こなしているという気質が感じられた。もしも、時代の波が変わり、手造りの良さが分かってくれる人が多くなれば、まだまだ仕事は増え、後継者も生まれるのではないだろうかと思う。 先生の作品を扱う問屋(先生の作品は一件の問屋で全て扱っている)の話である。
昨年(平成九年)先生は数回テレビに出て長板染を紹介された。深夜の若者向けの番組にも出演して、雑誌でも話題になったそうである。その後、全国から長板染に関する問い合わせが殺到して、中にはわざわざ遠くから訪ねてくる若い女性もいたという。
「なくなってしまうかもしれない野口先生のきものを一枚持っていたいので、柄はどんな柄でもいいですから一反譲ってほしい。」
と言って買って行くという。
「困ってしまいましたよ。」
という問屋の言葉である。先生の作品は製作に手間が掛かり、生産反数は限られている。一年間掛けて染められた作品はシーズン前に小売店に卸される。しかし、シーズン前にすでに商品が無くなってしまったという訳である。「困って・・・」というのは問屋の嬉しい悲鳴かもしれない。しかし、私はこの話を聞いて複雑な気持ちになった。
最近、若者の間にはブランド信仰とあいまって、希少品をもてはやす風潮がある。スポーツシューズや時計など人為的に希少性を演出されたものがプレミアムを付けられ高値で売買されている。はたからみれば、ばかばかしいような物でも希少価値とばかりに取り引きされている。
先生の作品を買い求める若い女性がどんな気持ちで買っていくのかは知る由もない。希少価値を求める風潮に踊らされているのか、あるいは先生の作品の本当の良さを知って買い求めているのか。私は後者であってほしいと願っている。
二時間ほど見学させてもらって工房を出た。玄関まで見送ってくれた先生に、
「せっかくですから一緒に写真を・・。」
と、言って『萬染物店』の看板の前で奥さんに写真を撮ってもらった。
「いや、私なんか・・・、うまく撮れますか・・・。」
と、少し照れながら『○×酒店』と書かれた前掛けを はずし、並んで写真に入ってくれた。
「向かいにバス亭があります。バスは全部駅に行きま すから。」
バス亭にはもうバスが近づいて来たので、挨拶もそ ぞろに私はバスにかけ乗った。
バスが門の前を過ぎるまで先生は門の前に立って見 送ってくれた。私もバスの中から挨拶をして別れた。
先生の素朴な人柄と生活。そして直向きに職人技を 守ろうとする姿勢に、私は現代の世がどこかに置き忘 れたものを先生は大切に抱えてくれているように思え てならなかった。

